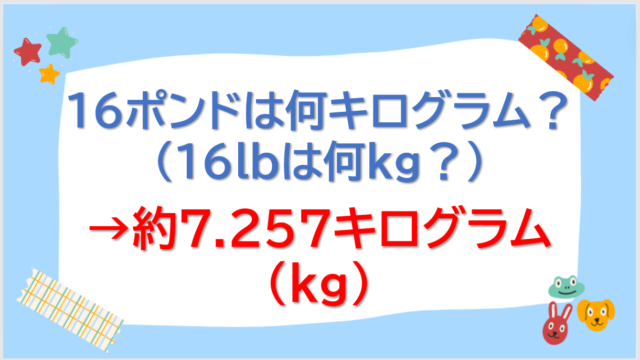DIYで細身のフレームや装飾パーツを作りたいとき、1×2材は非常に便利な木材です。棚の枠組み、ディスプレイラック、小物入れの骨組みなど、繊細な作品づくりに欠かせません。
しかし、1×4材や2×4材に比べると、1×2材の情報は意外と少ないものです。「実際のサイズはどれくらいなのか」「価格はいくらぐらいか」「どんな用途に向いているのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、1×2材の基本的なサイズや寸法、価格相場、さらには実際のDIYでの活用方法まで詳しく解説していきます。これから細かい木工作品に挑戦したい方や、より精密なDIYを楽しみたい方は、ぜひ参考にしてください。
1×2材の基本サイズと実寸法について
それではまず、1×2材の基本的なサイズと実寸法について解説していきます。
1×2材の規格サイズと実際の寸法
1×2材という名称は、厚みが1インチ、幅が2インチという規格を表しています。1インチは25.4mmですから、理論上は厚み25.4mm、幅50.8mmということになるでしょう。
しかし、実際にホームセンターで1×2材を手に取ると、表記よりも小さいサイズになっていることに気づきます。これは木材の加工工程で、表面を削って滑らかに仕上げるためです。
1×2材の実寸法
厚み:約19mm(表記は1インチ=25.4mm)
幅:約38mm(表記は2インチ=50.8mm)
実際の寸法は、厚みが約19mm、幅が約38mmとなります。規格サイズと実寸には常に差があるため、DIYの設計時には必ず実寸法で計算する必要があるでしょう。
特に1×2材は細身のため、数ミリの誤差が完成品の見た目に大きく影響します。購入前に実際のサイズをメジャーで確認することをおすすめします。
1×4材や2×4材との違い
1×2材は、他のサイズの木材とどのように違うのでしょうか。代表的な規格材と比較してみましょう。
| 規格サイズ | 厚み(実寸) | 幅(実寸) | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 1×2材 | 約19mm | 約38mm | フレーム、装飾材 |
| 1×4材 | 約19mm | 約89mm | 棚板、天板 |
| 2×4材 | 約38mm | 約89mm | 構造材、脚部 |
| 2×2材 | 約38mm | 約38mm | 柱、支柱 |
1×2材の特徴は、厚みは標準的ながら幅が細いという点です。このサイズ感が、繊細な作品づくりや装飾的なDIYに最適なのです。
2×4材のように構造材としての強度は期待できませんが、軽量で扱いやすく、細かい加工がしやすいというメリットがあります。用途に応じて使い分けることが重要でしょう。
1×2材が適した用途と活用例
1×2材は、その細身の特徴を活かした用途に適しています。具体的な活用例を見ていきましょう。
まず代表的な用途は、棚やラックのフレーム材です。1×4材で棚板を作り、その枠組みや補強材として1×2材を使うと、すっきりとした印象の棚が完成します。
1×2材の主な活用例
壁面ディスプレイの枠組み
小物収納ボックスの骨組み
写真立てやフォトフレーム
植物用のトレリスやラティス
窓枠の装飾モールディング
また、壁面に取り付けるウォールシェルフの受け材としても活躍します。目立たないサイズ感なので、インテリアの邪魔をせず機能的に使えるでしょう。
ガーデニング用途では、プランターボックスの枠や、つる性植物を這わせるトレリスにも最適です。細い材を格子状に組むことで、軽やかな印象の作品が作れます。
1×2材の長さバリエーションと選び方
続いては、1×2材の長さバリエーションと選び方を確認していきます。
ホームセンターで扱われている長さの種類
1×2材は、1×4材ほど長さのバリエーションが豊富ではありませんが、一般的なホームセンターでは以下の長さが扱われています。
| フィート表記 | ミリ表記 | 取り扱い状況 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 3f | 約910mm | 一部店舗のみ | 150〜250円 |
| 6f | 約1820mm | 一般的 | 200〜400円 |
| 8f | 約2440mm | 一般的 | 300〜550円 |
| 10f | 約3050mm | 取り寄せの場合も | 400〜700円 |
最も入手しやすいのは6フィート(約1820mm)と8フィート(約2440mm)です。店舗によっては1×2材の取り扱い自体が少ないこともあるため、事前に在庫を確認すると良いでしょう。
3フィート(約910mm)のような短い材は、カット済み商品として販売されていることもあります。小さな作品を作る際には便利です。
用途別の最適な長さの選び方
作りたいものによって、最適な長さは異なります。効率的な選び方のポイントを見ていきましょう。
小物入れや写真立てなど、小型の作品を作る場合は3〜6フィート材が適しています。無駄が少なく、作業もしやすいでしょう。
作品サイズ別の推奨長さ
30cm以下の小物:3f材または端材
50〜80cmの棚:6f材
1m以上の棚やラック:8f材
大型家具の補強材:8f以上
壁面ディスプレイラックや本棚のフレームなど、中型の家具には8フィート材がおすすめです。カット後の端材も別の小物づくりに活用できます。
複数の部材が必要な場合は、木取り図を作成して最も無駄の少ない購入計画を立てることが重要です。長さの違う材を組み合わせることで、コストを抑えられるでしょう。
カット済み商品と長尺材の使い分け
ホームセンターでは、規格の長さの他に、カット済みの短い1×2材が売られていることもあります。これらをうまく使い分けることで、作業効率が上がるでしょう。
カット済み商品のメリットは、持ち運びが楽で、すぐに使えることです。30cm、45cm、60cmといった使いやすい長さにカットされているものが一般的でしょう。
一方、長尺材を購入して自分でカットする方が、単価は安く、寸法の自由度も高いのです。ただし、カット作業の手間と工具が必要になります。
カット済み商品が向いているケース
工具を持っていない初心者
車が小さく長い材を運べない
すぐに組み立てたい小型作品
多くのホームセンターでは、購入した木材を有料でカットしてくれるサービスがあります。1カット50〜100円程度で、正確な直角カットをしてもらえるため、初心者には特におすすめです。
1×2材の価格相場と購入ガイド
続いては、1×2材の価格相場と購入ガイドを確認していきます。
木材の種類別価格比較
1×2材として販売されている木材には、いくつかの種類があります。それぞれの特徴と価格帯を理解して、用途に合った選択をしましょう。
SPF材は、針葉樹の混合材で、最も一般的な1×2材です。柔らかく加工しやすいため、DIY初心者に最適な選択肢と言えるでしょう。
| 木材の種類 | 6f材の価格 | 特徴 | 適した用途 |
|---|---|---|---|
| SPF材 | 200〜400円 | 加工しやすい、入手容易 | 一般的なDIY全般 |
| ホワイトウッド | 180〜350円 | 安価、節が多い | 塗装前提の作品 |
| 杉材 | 300〜500円 | 香りが良い、軽量 | 屋内用家具 |
| ヒノキ材 | 400〜700円 | 耐久性高い、高級感 | 長期使用する家具 |
ホワイトウッドはSPF材よりも安価ですが、節が多く反りやすい傾向があります。ペイント仕上げにする作品であれば、コストパフォーマンスは良いでしょう。
杉材やヒノキ材は国産材で、香りが良く調湿効果もあります。価格は高めですが、長く使う家具や和風の作品には適した選択です。
ホームセンター別の価格傾向
同じ1×2材でも、購入するホームセンターによって価格は変わってきます。主要なホームセンターの価格傾向を見てみましょう。
大型のホームセンターチェーンでは、SPF材の6フィート1×2材が250〜350円程度で販売されています。会員価格やポイント還元を含めると、さらにお得になるでしょう。
地域密着型の小規模店では、やや価格は高めですが、品質の良い国産材を扱っていることも多いのです。木材選びのアドバイスも受けやすいというメリットがあります。
価格比較のポイント
大型チェーン店:品揃え豊富、価格競争力あり
専門店:品質重視、アドバイス充実
オンライン:比較しやすいが送料に注意
オンラインショップでの購入も選択肢の一つです。ただし、送料が高額になる場合があるため、複数本まとめて購入する際に検討すると良いでしょう。
時期によっても価格は変動します。輸入材は為替の影響を受けやすく、また春先や秋口のDIYシーズンには若干高くなる傾向があります。
お得に購入するためのポイント
1×2材をお得に購入するためには、いくつかのコツがあります。賢い買い物のテクニックを紹介しましょう。
まず、B級品や端材コーナーをチェックすることをおすすめします。小さな節や軽微な傷があるだけで、通常価格の半額以下で購入できることもあるのです。
ホームセンターの会員になると、定期的な割引クーポンやポイント還元が受けられます。年に数回しかDIYをしない方でも、会員登録する価値はあるでしょう。
コストを抑える4つの方法
1. B級品や端材を積極的に活用する
2. セール期間やまとめ買いを利用する
3. 長材を購入して自分でカットする
4. 複数の作品を同時に計画して無駄なく使う
また、複数の作品を同時に計画することで、木材を無駄なく使い切れます。端材も小物作りに活用すれば、材料費を大幅に節約できるでしょう。
友人やDIY仲間と共同購入するのも良い方法です。長尺材を分け合うことで、一人当たりのコストを下げられます。
1×2材を使ったDIYの実践テクニック
続いては、1×2材を使ったDIYの実践テクニックを確認していきます。
加工時の注意点と必要な工具
1×2材は細身のため、加工時には特別な注意が必要です。適切な工具と技術を使って、正確な作品を作りましょう。
基本的な工具としては、のこぎりまたは電動丸ノコ、サンドペーパー、メジャー、さしがね、クランプなどが必要です。1×2材は細いので、カット時にしっかり固定しないとズレやすいのです。
電動工具を使う場合は、必ず保護メガネを着用してください。細い材は跳ねやすく、目に木片が入るリスクが高まります。
1×2材加工の基本手順
1. 正確に寸法を測定してマーキングする
2. クランプでしっかり固定する
3. さしがねで直角を確認する
4. ゆっくり丁寧にカットする
5. サンドペーパーで切断面を整える
特に斜めカット(マイターカット)をする際は、マイターボックスやマイターソーを使うと正確な角度が出せます。額縁のような作品を作る場合には必須の工具でしょう。
また、1×2材は細いため、ビス留めの際には必ず下穴を開けてください。下穴なしでビスを打つと、ほぼ確実に木材が割れてしまいます。
接合方法と強度を高めるコツ
1×2材は細身のため、接合方法の選択が作品の強度に大きく影響します。用途に応じた適切な接合方法を選びましょう。
最も基本的な接合方法は、ビス留めです。ただし、1×2材の場合は細いビス(2.5mm〜3mm程度)を使い、下穴を開けることが必須でしょう。
| 接合方法 | 強度 | 作業難易度 | 適した用途 |
|---|---|---|---|
| ビス留め | 中 | 易 | 一般的なフレーム |
| 木工用ボンド併用 | 高 | 中 | 強度が必要な接合 |
| ダボ接合 | 高 | 難 | 見た目重視の作品 |
| 釘打ち | 中 | 易 | 仮組みや軽量物 |
強度を高めるには、ビス留めと木工用ボンドを併用するのが効果的です。ボンドを塗ってからビスで固定し、ボンドが完全に乾燥するまで待ちましょう。
強度を高める3つのポイント
1. 接合部にはボンドを併用する
2. 複数箇所で固定して荷重を分散させる
3. 補強材や金具を適宜使用する
角部分の接合には、L字金具やコーナーブラケットを使うと強度が大幅に向上します。特に棚などの実用的な家具では、金具の使用をおすすめします。
ダボ接合は見た目が美しい接合方法ですが、正確な穴あけが必要なため、ダボ用ジグを使うと良いでしょう。
塗装と仕上げの基本
1×2材を使った作品を美しく仕上げるには、適切な塗装が欠かせません。細身の材だからこそ、丁寧な仕上げが見た目の印象を左右します。
まず、組み立て前に各パーツをサンディングしましょう。粗目(#120)から細目(#240〜#320)へと段階的に番手を上げることで、滑らかな表面が得られます。
塗装の種類は、作品の用途と好みで選びます。ナチュラルな木目を活かしたい場合は、ステインやオイルフィニッシュがおすすめです。
塗装の基本プロセス
1. サンディングで表面を滑らかにする
2. 木くずを完全に拭き取る
3. 下塗り材を薄く塗る(必要に応じて)
4. 十分に乾燥させる(24時間以上)
5. 軽くサンディングして上塗りを重ねる
カラフルな仕上げにしたい場合は、水性塗料が扱いやすいでしょう。薄く複数回塗り重ねることで、ムラのない美しい仕上がりになります。
細い材なので、塗料が垂れやすい点に注意が必要です。横向きに置いて塗装し、一面ずつ乾燥させてから次の面に進む方法がおすすめです。
ワックス仕上げは、使い込むほどに味わいが増します。特にヴィンテージ風の作品を作りたい場合には、オイルステイン後にワックスを塗ると良い雰囲気が出るでしょう。
まとめ
1×2材は、厚み約19mm、幅約38mmという細身のサイズが特徴の木材です。フレーム材や装飾材として、繊細なDIY作品づくりに欠かせません。
価格相場はSPF材の6フィートで200〜400円程度と、比較的リーズナブルです。ただし、1×4材に比べて取り扱い店舗が限られることもあるため、事前の在庫確認をおすすめします。
加工時は細身ゆえの注意点があり、しっかり固定すること、下穴を開けること、適切な接合方法を選ぶことが重要でしょう。丁寧な仕上げを施すことで、美しく実用的な作品が完成します。
1×2材の特性を理解して、ぜひ繊細で魅力的なDIY作品づくりに挑戦してみてください。