流体力学や流体計測を学ぶ上で重要な測定器の一つがピトー管です。飛行機の速度計測、風洞実験、配管内の流速測定など、流体の速度を知るためには、ピトー管の知識が欠かせません。
しかし、ピトー管とは何を測定する装置なのでしょうか。どんな原理で流速を測定するのか、どうやって計算するのか、わかりにくいと感じる方も多いはずです。
実は、ピトー管は流体の動圧と静圧の差を利用して流速を測定する装置であり、ベルヌーイの定理に基づく最も基本的な流速計となります。
航空機の速度計として実用化されて以来、様々な分野で広く使われているのです。
この記事では、ピトー管の基本的な定義から、測定原理と仕組み、ベルヌーイの定理との関係、流速の計算公式、ピトー管係数、そしてマノメータを使った具体的な計算例題まで、わかりやすく丁寧に解説していきます。
流体力学や機械工学を学ぶ方はぜひ最後までお読みください。
ピトー管とは?基本的な意味と定義
それではまず、ピトー管の基本的な意味と定義について解説していきましょう。
ピトー管の定義
ピトー管(ピトーかん、英語:Pitot tube)とは、流体の流速を測定するための管状の測定器です。
フランスの物理学者アンリ・ピトー(Henri Pitot)が1732年に発明しました。
ピトー管の特徴:
・流体の動圧と静圧を同時に測定
・圧力差から流速を計算
・構造がシンプル
・比較的安価
・広範囲の流速測定が可能
ピトー管は、次のような場面で使われています。
・航空機の速度計(対気速度計)
・風洞実験での風速測定
・配管内の流速測定
・換気ダクトの風速測定
・河川の流速測定
例えば、飛行機の機首や翼に取り付けられている細い管がピトー管。これにより、飛行機の対気速度を正確に測定できるのです。
ピトー管は、流体力学の実験、産業プロセスの監視、環境測定など、様々な分野で不可欠な測定器となっています。
ピトー管の構造
ピトー管の基本構造は非常にシンプルです。
基本的な構成要素:
・全圧管(動圧管):流体に正面から向けた管
・静圧孔:流体の流れに平行な側面の穴
・圧力測定装置:マノメータや圧力計
全圧管(よどみ点):
・流れに正対して開口
・流体がぶつかって静止する点
・全圧(動圧 + 静圧)を測定
静圧孔:
・流れに平行な側面に開けた穴
・流体の流れを乱さない位置
・静圧のみを測定
2つの圧力の差が動圧となり、これから流速を求めることができます。
ピトー管の種類
ピトー管にはいくつかの種類があります。
ピトー管(単純型):
・全圧のみを測定
・別に静圧測定が必要
・最も単純な構造
ピトー静圧管(ピトー・スタティック管):
・全圧と静圧を同時に測定
・1本の管で完結
・航空機で広く使用
・最も一般的なタイプ
ケルピトー管:
・L字型の構造
・狭い場所での測定に適する
・配管内測定で使用
ピトー静圧管が最もよく使われるため、単に「ピトー管」と言えばこのタイプを指すことが多いでしょう。
・流体の流速を測定する装置
・動圧と静圧の差を利用
・構造がシンプルで安価
・航空機や配管で広く使用
ピトー管の原理と仕組み
続いては、ピトー管が流速を測定する原理と仕組みについて確認していきましょう。
ベルヌーイの定理
ピトー管の測定原理は、ベルヌーイの定理に基づいています。
ベルヌーイの定理は、流体のエネルギー保存則を表す式です。
ここで、
・P:静圧 [Pa]
・ρ:流体の密度 [kg/m³]
・v:流速 [m/s]
・g:重力加速度 = 9.8 m/s²
・h:高さ [m]
この式の各項の意味:
・P:圧力エネルギー(静圧)
・(1/2)ρv²:運動エネルギー(動圧)
・ρgh:位置エネルギー
水平な流れ(高さhが一定)では、
つまり、流速が速いところでは圧力が低く、流速が遅いところでは圧力が高くなるのです。
よどみ点と全圧
ピトー管の開口部では、流体が正面からぶつかって静止します。
この点をよどみ点(stagnation point)と呼びます。
よどみ点での流速:v = 0
ベルヌーイの定理から、
よどみ点:P₀ + (1/2)ρ × 0² = P₀
したがって、
P₀ = P₁ + (1/2)ρv₁²
ここで、
・P₀:よどみ点の圧力(全圧)
・P₁:流れの中の圧力(静圧)
・v₁:流れの速度
全圧P₀は、静圧P₁と動圧(1/2)ρv₁²の和。
動圧と流速の関係
全圧と静圧の差が動圧です。
この式を変形すると、流速vが求まります。
v² = 2(P₀ – P₁)/ρ
v = √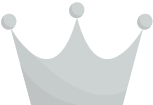
これが、ピトー管による流速測定の基本式。
測定の手順:
1. ピトー管で全圧P₀を測定
2. 静圧孔で静圧P₁を測定
3. 圧力差ΔP = P₀ – P₁を求める
4. 流体の密度ρを確認
5. 公式に代入して流速vを計算
ピトー管はこのように、圧力の測定から流速を間接的に求める装置なのです。
・ベルヌーイの定理に基づく
・よどみ点で全圧を測定
・静圧孔で静圧を測定
・圧力差から流速を計算
・v = √
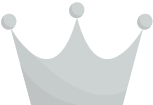
流速の計算公式とピトー管係数
続いては、ピトー管を使った流速の計算方法を見ていきましょう。
理想的なピトー管の計算式
理想的な(損失のない)ピトー管では、次の式で流速を計算します。
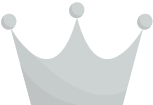
または、
v = √(2ΔP/ρ)
ここで、
・v:流速 [m/s]
・P₀:全圧 [Pa]
・P₁:静圧 [Pa]
・ΔP = P₀ – P₁:圧力差(動圧)[Pa]
・ρ:流体の密度 [kg/m³]
この式は、理想流体(粘性のない流体)で、ピトー管が完全な形状の場合に成り立ちます。
ピトー管係数
実際のピトー管では、測定誤差や流れの乱れなどの影響があります。
これを補正するために、ピトー管係数Cを導入します。
ここで、
・C:ピトー管係数(無次元)
ピトー管係数Cの典型的な値:
・理想的なピトー管:C = 1.00
・標準的なピトー静圧管:C = 0.98〜1.02
・よく校正されたピトー管:C = 1.00 ± 0.01
・粗い製作のピトー管:C = 0.95〜1.05
高精度な測定では、個別に校正してC値を決定します。
一般的な計算では、C = 1.0として扱うことが多いでしょう。
マノメータを使った測定
圧力差ΔPの測定には、マノメータ(manometer、液柱圧力計)がよく使われます。
U字管マノメータの場合:
ここで、
・ρₘ:マノメータ液の密度 [kg/m³]
・ρ:測定流体の密度 [kg/m³]
・g:重力加速度 = 9.8 m/s²
・h:液柱の高さの差 [m]
これを流速の式に代入すると、
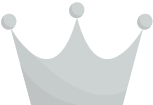
気体の測定でρ ≪ ρₘの場合、
v ≈ √(2ρₘgh/ρ)
よく使われるマノメータ液:
・水:ρₘ = 1000 kg/m³
・水銀:ρₘ = 13,600 kg/m³
・アルコール:ρₘ = 800 kg/m³
・油:ρₘ = 850〜900 kg/m³
単位系の注意点
計算では単位の統一が重要です。
SI単位系での計算:
・圧力:Pa(N/m²)
・密度:kg/m³
・流速:m/s
・長さ:m
よく使われる単位換算:
1 bar = 100,000 Pa
1 mmHg = 133.3 Pa
1 mmH₂O = 9.8 Pa
計算時の注意:
・すべての値をSI単位に統一
・特に圧力の単位に注意
・密度は測定温度での値を使う
・重力加速度g = 9.8 m/s²(または9.81 m/s²)
| 記号 | 名称 | 単位 |
|---|---|---|
| v | 流速 | m/s |
| ΔP | 圧力差(動圧) | Pa |
| ρ | 流体密度 | kg/m³ |
| C | ピトー管係数 | 無次元 |
| h | マノメータ液柱差 | m |
これらの公式と単位を正しく使うことが、正確な流速計算の基礎となります。
ピトー管の計算例題
続いては、ピトー管を使った具体的な計算例題を見ていきましょう。
基本的な流速計算
まずは、圧力差から直接流速を求める基本問題です。
標準状態の空気(密度ρ = 1.2 kg/m³)をピトー管で測定したところ、圧力差ΔP = 300 Paだった。流速は?(ピトー管係数C = 1.0とする)
v = C√(2ΔP/ρ)
= 1.0 × √(2 × 300 / 1.2)
= √(600 / 1.2)
= √500
≈ 22.4 m/s
流速は約22.4 m/s。
水(密度ρ = 1000 kg/m³)をピトー管で測定したところ、圧力差ΔP = 5000 Paだった。流速は?
v = √(2ΔP/ρ)
= √(2 × 5000 / 1000)
= √(10000 / 1000)
= √10
≈ 3.16 m/s
流速は約3.16 m/s。
マノメータを使った計算
マノメータの液柱差から流速を求める問題です。
空気(密度ρ = 1.2 kg/m³)の流速をピトー管で測定し、水マノメータ(ρₘ = 1000 kg/m³)を接続したところ、液柱差h = 50 mm = 0.05 mだった。流速は?
空気の密度は水に比べて非常に小さいので、ρ ≪ ρₘとして、
v ≈ √(2ρₘgh/ρ)
= √(2 × 1000 × 9.8 × 0.05 / 1.2)
= √(980 / 1.2)
= √816.7
≈ 28.6 m/s
流速は約28.6 m/s。
空気(密度ρ = 1.2 kg/m³)の流速をピトー管で測定し、水銀マノメータ(ρₘ = 13,600 kg/m³)を接続したところ、液柱差h = 10 mm = 0.01 mだった。流速は?
v ≈ √(2ρₘgh/ρ)
= √(2 × 13600 × 9.8 × 0.01 / 1.2)
= √(2666.4 / 1.2)
= √2222
≈ 47.1 m/s
流速は約47.1 m/s。
水銀は密度が高いので、小さな液柱差でも大きな流速を測定できる。
ピトー管係数を考慮した計算
実際の測定では、ピトー管係数を考慮します。
ピトー管係数C = 0.98のピトー管を使って、空気(ρ = 1.2 kg/m³)の流速を測定したところ、圧力差ΔP = 400 Paだった。実際の流速は?
v = C√(2ΔP/ρ)
= 0.98 × √(2 × 400 / 1.2)
= 0.98 × √(800 / 1.2)
= 0.98 × √666.7
= 0.98 × 25.8
≈ 25.3 m/s
実際の流速は約25.3 m/s。
もしC = 1.0として計算すると25.8 m/sとなり、約2%の誤差が生じる。
航空機の速度計算
航空機での応用例です。
高度3000 mを飛行中の航空機のピトー管が、圧力差ΔP = 8000 Paを示した。この高度での空気密度がρ = 0.9 kg/m³のとき、対気速度は?
v = √(2ΔP/ρ)
= √(2 × 8000 / 0.9)
= √(16000 / 0.9)
= √17778
≈ 133 m/s
対気速度は約133 m/s ≈ 479 km/h。
配管内流速の計算
配管内の流速測定の例です。
直径300 mmの配管内の水の流速をピトー管で測定したところ、圧力差ΔP = 2000 Paだった。流速と流量は?(水の密度ρ = 1000 kg/m³)
流速:
v = √(2ΔP/ρ)
= √(2 × 2000 / 1000)
= √4
= 2.0 m/s
流量:
配管の断面積 A = π × (0.3/2)² = π × 0.0225 ≈ 0.0707 m²
流量 Q = v × A = 2.0 × 0.0707 ≈ 0.141 m³/s
流速は2.0 m/s、流量は約0.141 m³/s(約141 L/s)。
・v = √(2ΔP/ρ) が基本式
・マノメータ使用時:v ≈ √(2ρₘgh/ρ)
・単位をSI単位系に統一
・ピトー管係数Cを考慮(通常1.0前後)
・流量Q = v × A(断面積)
これらの計算方法をマスターすれば、様々な流速測定の問題が解けるでしょう。
ピトー管の測定誤差と注意点
続いては、ピトー管を使用する際の測定誤差や注意点を確認していきましょう。
測定誤差の要因
ピトー管による測定には、いくつかの誤差要因があります。
設置位置の誤差:
・流れに対して正確に向ける必要がある
・5度以上の傾きで誤差が増加
・10度の傾きで約1%の誤差
・壁面近くでは流速分布の影響
流れの乱れ:
・乱流の影響で圧力が変動
・測定値の時間平均が必要
・脈動流では誤差が大きい
レイノルズ数の影響:
・低レイノルズ数(Re 1000)では精度良好
圧縮性の影響:
・気体の高速流(マッハ数 > 0.3)では補正が必要
・非圧縮性の仮定が成り立たない
・航空機の高速飛行で重要
測定精度を上げる方法
より正確な測定のための工夫:
・ピトー管を流れに正確に向ける
・十分な助走区間を確保
・管壁から離れた位置で測定
・複数点での測定と平均化
・校正されたピトー管を使用
・適切なマノメータの選択
・温度補正(密度の温度依存性)
ピトー管の利点と欠点
利点
:
・構造がシンプル
・安価で入手しやすい
・広範囲の流速測定が可能
・流れを大きく乱さない
・保守が容易
・長期間使用可能
欠点:
・低速流の測定が困難(圧力差が小さい)
・正確な向きの設定が必要
・1点測定(流速分布は測定できない)
・詰まりやすい(微粒子を含む流体)
・応答が遅い(圧力伝達の遅れ)
・凍結の危険(航空機での着氷)
・流れに正対させる(±5度以内)
・十分なレイノルズ数を確保
・定期的な校正
・詰まりの防止
・温度補正を忘れない
これらの点に注意することで、より正確な流速測定が可能となります。
まとめ
ピトー管について、基本的な定義から測定原理、計算方法、具体的な例題、測定上の注意点まで詳しく解説してきました。
ピトー管は、流体の動圧と静圧の差を利用して流速を測定する装置であり、ベルヌーイの定理に基づいています。
測定原理は、よどみ点で全圧を測定し、静圧孔で静圧を測定し、その差(動圧)から流速を計算するもの。
流速の計算式はv = C√(2ΔP/ρ)であり、Cはピトー管係数(通常1.0前後)、ΔPは圧力差、ρは流体密度です。
マノメータを使う場合は、v ≈ √(2ρₘgh/ρ)の式を使い、液柱差hから流速を求めることができます。
測定では、設置角度、流れの乱れ、レイノルズ数、圧縮性などの影響を考慮する必要があるでしょう。
航空工学、流体力学、機械工学、環境工学など、多くの分野でピトー管の知識が必要です。
この記事で学んだ知識を使って、流速測定の理解を深めてください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上、同じ形式でピトー管の記事が完成いたしました!
ご確認くださいませ😊





