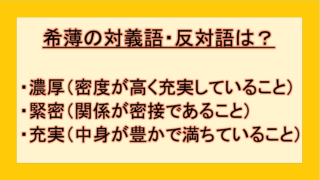DIYで木工作品を作る際、最も使用頻度が高い木材の一つが1×4材です。棚やラック、テーブル、収納ボックスなど、さまざまな用途に活用できる汎用性の高さが魅力でしょう。
しかし、初めてDIYに挑戦する方にとって、「1×4」という表記や「6f」「12f」といった長さの単位は分かりにくいものです。また、ホームセンターに行っても、実際のサイズが表記と違うことに戸惑う方も多いのではないでしょうか。
本記事では、1×4材の基本的なサイズや寸法、フィート表記の読み方、さらには価格相場まで詳しく解説していきます。これからDIYを始める方はもちろん、より効率的に木材を選びたい方にも役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。
1×4材の基本サイズと寸法について
それではまず、1×4材の基本的なサイズと寸法について解説していきます。
1×4材の規格サイズと実寸法
1×4材という名称は、厚みが1インチ、幅が4インチという規格を示しています。インチをミリメートルに換算すると、1インチは約25.4mmです。
しかし、実際にホームセンターで1×4材を測ってみると、表記とは異なるサイズになっていることに気づくでしょう。これは、木材の加工過程で表面を削って仕上げるためです。
1×4材の実寸法
厚み:約19mm(表記は1インチ=25.4mm)
幅:約89mm(表記は4インチ=101.6mm)
実際の寸法は、厚みが約19mm、幅が約89mmとなります。この差は、製材後の乾燥や表面加工によって生じるもので、規格上の表記と実寸には常に違いがある点を理解しておく必要があります。
DIYで設計図を描く際は、必ず実寸法を基準に計算しましょう。表記サイズで計算してしまうと、完成した作品のサイズが予定より小さくなってしまいます。
インチ表記とミリ表記の違い
木材のサイズ表記には、インチ表記とミリ表記の2種類があります。1×4材はインチ表記の代表例ですが、日本のホームセンターではミリ表記も併記されていることが多いでしょう。
| 表記方法 | 厚み | 幅 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| インチ表記 | 1インチ | 4インチ | アメリカ規格、DIY向け |
| ミリ表記(実寸) | 19mm | 89mm | 実際の寸法 |
| ミリ表記(規格) | 25.4mm | 101.6mm | 加工前の理論値 |
インチ表記は主にSPF材などの輸入木材で使われます。一方、国産材の場合は最初からミリ表記で販売されることもあるでしょう。
購入時は必ず実寸を確認することが重要です。同じ1×4材でも、メーカーや木材の種類によって微妙にサイズが異なる場合があります。
長さの種類と用途別の選び方
1×4材は、厚みと幅は規格で決まっていますが、長さはさまざまな種類が用意されています。一般的なホームセンターで扱われている長さは以下の通りです。
代表的な1×4材の長さ
6フィート(6f):約1820mm
8フィート(8f):約2438mm
10フィート(10f):約3048mm
12フィート(12f):約3658mm
用途別の選び方としては、小物や棚板には6f、テーブルの天板や長めの棚には8f以上が適しています。長い材料を購入してカットする方が、複数の短い材料を買うよりコストパフォーマンスが良い場合も多いでしょう。
ただし、長い木材は運搬や保管が大変です。自家用車のサイズや作業スペースを考慮して、適切な長さを選ぶことをおすすめします。
6f・12fなどの長さ表記と実際のサイズ
続いては、6fや12fといった長さ表記と実際のサイズを確認していきます。
フィート表記の読み方と換算方法
木材の長さで使われる「f」は、フィート(feet)の略称です。1フィートは約304.8mmに相当します。
フィートからミリメートルへの換算は、以下の計算式で求められるでしょう。
フィートからミリへの換算式
長さ(mm)= フィート数 × 304.8
例:6フィートの場合
6 × 304.8 = 1828.8mm(約1820mm)
実際の商品では、端数を切り捨てて1820mmや1830mmと表記されることが一般的です。厳密な寸法が必要な場合は、購入前に実測することをおすすめします。
また、フィート表記に慣れていない方は、おおよその長さを覚えておくと便利でしょう。6fは約1.8m、8fは約2.4m、12fは約3.6mと覚えておくと、買い物の際にイメージしやすくなります。
6f・8f・10f・12fの実寸比較
各長さの実寸を比較してみましょう。以下の表で、フィート表記とミリメートル表記の対応を確認できます。
| フィート表記 | 理論値(mm) | 実際の表記(mm) | メートル換算 |
|---|---|---|---|
| 6f | 1828.8mm | 約1820mm | 約1.82m |
| 8f | 2438.4mm | 約2440mm | 約2.44m |
| 10f | 3048.0mm | 約3050mm | 約3.05m |
| 12f | 3657.6mm | 約3660mm | 約3.66m |
購入する際は、作りたいものの寸法に対して少し余裕を持った長さを選ぶことが大切です。カットする際の誤差や、木材の端部に傷がある場合の予備を考慮しましょう。
長さ別の使い分けポイント
それぞれの長さには、適した用途があります。効率的に木材を使うための使い分けポイントを見ていきましょう。
6フィート材は、小型の棚やボックス、椅子の部材などに最適です。持ち運びしやすく、軽自動車でも運搬できるサイズ感が魅力でしょう。
8フィート材は、汎用性が最も高い長さと言えます。テーブルの天板、本棚の側板、ベンチなど、中型の家具作りに向いています。
長さ選びの基本ルール
必要な長さ+カット誤差(5〜10mm)+予備(50〜100mm)=購入する長さ
10フィート以上の長材は、大型家具や連続した長い棚板が必要な場合に選びます。ただし、車への積載や作業スペースの確保が課題となるため、事前の計画が重要です。
複数の部材が必要な場合は、木取り図を作成して、どの長さを何本購入すれば無駄が少ないか計算しましょう。
1×4材の価格相場と購入時のポイント
続いては、1×4材の価格相場と購入時のポイントを確認していきます。
ホームセンター別の価格比較
1×4材の価格は、ホームセンターや木材の種類によって大きく異なります。2024年時点での一般的な価格相場を見てみましょう。
| 長さ | SPF材 | ホワイトウッド | 杉材 |
|---|---|---|---|
| 6f(約1820mm) | 300〜500円 | 250〜400円 | 400〜600円 |
| 8f(約2440mm) | 400〜650円 | 350〜550円 | 550〜800円 |
| 12f(約3660mm) | 650〜1000円 | 550〜850円 | 900〜1300円 |
価格は時期や地域、木材の品質によって変動
します。特に、為替レートの影響を受けやすい輸入材は、価格が変わりやすい傾向にあるでしょう。
大手ホームセンターでは、会員割引やポイント還元があることも多いため、定期的にDIYを楽しむ方は会員登録がおすすめです。
木材の種類による価格差
1×4材として販売されている木材には、いくつかの種類があります。それぞれの特徴と価格帯を理解しておくと、用途に応じた選択ができるでしょう。
SPF材は、スプルース、パイン、ファーの3種類の針葉樹の総称です。柔らかく加工しやすいため、DIY初心者に最適な木材と言えます。価格も比較的リーズナブルで、入手しやすいのが特徴です。
ホワイトウッドは、SPF材よりもさらに価格が安い傾向にあります。ただし、節が多かったり反りやすかったりするため、用途を選ぶ必要があるでしょう。
木材選びのポイント
屋内用家具:SPF材、杉材がおすすめ
屋外用:防腐処理済みの木材を選ぶ
見た目重視:節の少ない上級グレードを選ぶ
コスト重視:ホワイトウッドやB級品も検討
杉材は国産材の代表格で、香りが良く調湿効果もあります。価格はやや高めですが、長く使う家具には適した選択でしょう。
コストを抑える購入のコツ
DIYのコストを抑えるためには、木材の購入方法にもコツがあります。いくつかの節約テクニックを紹介しましょう。
まず、長い木材を購入してカットする方が単価は安くなる傾向にあります。例えば、6f材を2本買うよりも、12f材を1本買ってカットする方がお得な場合が多いでしょう。
また、ホームセンターの端材コーナーやB級品をチェックするのもおすすめです。小さな節や軽微な傷があるだけで、半額以下で購入できることもあります。
セール期間を狙うのも有効な方法です。多くのホームセンターでは、週末や月末にDIY関連商品のセールを実施しています。
お得に購入する3つのポイント
1. 長材を購入して自分でカットする
2. B級品や端材を活用する
3. セール時期やまとめ買いを利用する
さらに、複数の作品を同時に計画して、木材をまとめ買いすることで配送料を節約できます。無駄なく使い切る設計を心がけましょう。
DIYで1×4材を使う際の注意点
続いては、DIYで1×4材を使う際の注意点を確認していきます。
加工時の注意事項と必要な工具
1×4材を加工する際には、適切な工具と安全対策が必要です。基本的な工具としては、のこぎりまたは電動丸ノコ、サンドペーパー、メジャー、さしがねなどが挙げられます。
カットする際は、必ず寸法を2回以上確認してから切断しましょう。「測り間違い」はDIY初心者が最も陥りやすい失敗です。
電動工具を使用する場合は、必ず保護メガネと防塵マスクを着用してください。木くずが目に入ったり、細かい粉塵を吸い込んだりするリスクがあります。
基本の加工工程
1. 寸法を測定して印をつける
2. さしがねで直角を確認する
3. カット線に沿って丁寧に切断する
4. 切断面をサンドペーパーで整える
5. 組み立て前に仮組みで確認する
また、ビス留めをする際は、下穴を開けることをおすすめします。下穴なしでビスを打ち込むと、木材が割れる原因となるでしょう。
反りや割れを防ぐ保管方法
木材は生き物のように、湿度や温度の変化に反応します。購入後の保管方法が適切でないと、反りや割れが発生してしまうでしょう。
保管する際は、平らな場所に水平に置き、複数枚を重ねる場合は間に桟木を挟むことが重要です。これにより、空気の流れが確保され、均等に乾燥が進みます。
直射日光が当たる場所や、エアコンの風が直接当たる場所は避けましょう。急激な乾燥は、反りや割れの原因となります。
| 保管環境 | 適切な条件 | 避けるべき条件 |
|---|---|---|
| 温度 | 15〜25℃程度 | 急激な温度変化 |
| 湿度 | 40〜60%程度 | 高湿度、極端な乾燥 |
| 置き方 | 水平、桟木使用 | 立てかけ、積み重ね |
| 場所 | 風通しの良い日陰 | 直射日光、雨ざらし |
購入してから加工するまでに時間がある場合は、作業場所で数日間「養生」させることをおすすめします。環境に木材を慣らすことで、完成後の変形を防げるでしょう。
塗装と仕上げのポイント
1×4材を使った作品を長持ちさせるためには、適切な塗装と仕上げが欠かせません。塗装には、保護機能と美観向上の両方の役割があります。
まず、組み立て前にサンドペーパーで表面を整えましょう。粗目(#80〜#120)から細目(#240〜#400)へと段階的に番手を上げることで、滑らかな仕上がりになります。
塗装の種類は、用途に応じて選びます。屋内用家具なら水性塗料やオイルフィニッシュ、屋外用ならウレタン塗料や防腐防虫塗料が適しているでしょう。
塗装の基本手順
1. サンディングで表面を整える
2. 木くずを完全に除去する
3. 下塗り(必要に応じて)
4. 十分に乾燥させる
5. 中塗り〜上塗りを重ねる
塗装は薄く複数回に分けて塗り重ねることが、美しい仕上がりのコツです。一度に厚く塗ると、ムラになったり乾燥に時間がかかったりします。
また、塗装後は完全に乾燥するまで触らないようにしましょう。表面が乾いていても、内部まで硬化するには数日かかる場合があります。
まとめ
1×4材は、DIYで最も使いやすい木材の一つです。厚み約19mm、幅約89mmという実寸法を理解し、6f、8f、12fといった長さ表記を把握すれば、効率的な材料選びができるでしょう。
価格相場は木材の種類や長さによって異なりますが、SPF材の6fで300〜500円程度が一般的です。コストを抑えるには、長材を購入してカットする、B級品を活用する、セール時期を狙うなどの工夫が有効でしょう。
加工する際は適切な工具を使い、保管時は反りや割れを防ぐ環境を整えることが大切です。そして、塗装や仕上げを丁寧に行うことで、長く愛用できる作品が完成します。
これらのポイントを押さえて、1×4材を使った素敵なDIY作品づくりに挑戦してみてください。