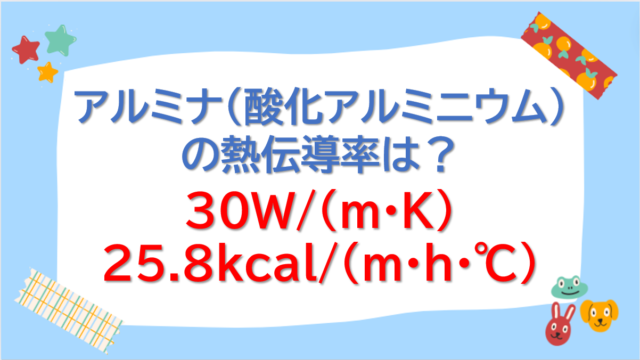化学反応論や物理化学を学ぶ上で最も重要な概念の一つが活性化エネルギーです。反応速度、触媒の効果、酵素の働き、温度依存性など、化学反応を理解するためには、活性化エネルギーの知識が欠かせません。
しかし、活性化エネルギーとは何を表しているのでしょうか。どんな単位で表されるのか、どうやって求めるのか、わかりにくいと感じる方も多いはずです。
実は、活性化エネルギーは化学反応が進むために必要な最小限のエネルギーであり、反応の速さや温度依存性を決める重要な指標となります。
触媒や酵素は活性化エネルギーを下げることで、反応を速く進めることができるのです。
この記事では、活性化エネルギーの基本的な定義から、単位や記号、求め方、アレニウスの式との関係、触媒や酵素の効果、そして様々な反応の活性化エネルギーの文献値一覧まで、わかりやすく丁寧に解説していきます。
化学や生化学を学ぶ方はぜひ最後までお読みください。
活性化エネルギーとは?基本的な意味と定義
それではまず、活性化エネルギーの基本的な意味と定義について解説していきましょう。
活性化エネルギーの定義
活性化エネルギー(かっせいかエネルギー、英語:activation energy)とは、化学反応が起こるために必要な最小限のエネルギーのことです。
記号ではEaで表されます。
化学反応が進むためには、反応物がある「エネルギーの山」を越える必要があります。
この山の高さが活性化エネルギーEa。
山が高い(Eaが大きい)反応:
・反応が起こりにくい
・高いエネルギー障壁を越える必要がある
・温度の影響を強く受ける
・触媒の効果が大きい
山が低い(Eaが小さい)反応:
・反応が起こりやすい
・低いエネルギー障壁を越えればよい
・温度の影響を受けにくい
・触媒の効果が小さい
例えば、紙が燃える反応は活性化エネルギーが大きいため、常温では起こりません。しかし、マッチの火で活性化エネルギーを与えると、反応が始まって燃え続けるのです。
活性化エネルギーは、化学反応の速度予測、触媒の設計、酵素反応の理解など、様々な分野に欠かせない概念となっています。
反応座標とエネルギー図
活性化エネルギーは、反応座標図(エネルギー図)で視覚的に理解できます。
反応座標図の構成要素:
・横軸:反応の進行度(反応座標)
・縦軸:エネルギー
・出発点:反応物のエネルギー
・最高点:遷移状態のエネルギー
・終点:生成物のエネルギー
活性化エネルギーEaは、反応物から遷移状態までのエネルギー差。
反応熱ΔHは、反応物と生成物のエネルギー差。
重要なポイント:
・Eaと反応熱ΔHは独立している
・発熱反応でもEaは大きい場合がある
・吸熱反応でもEaは小さい場合がある
遷移状態と活性化エネルギー
化学反応が進むとき、反応物は遷移状態(活性化複合体)と呼ばれる高エネルギー状態を経由します。
遷移状態の特徴:
・反応過程で最もエネルギーが高い状態
・反応物でも生成物でもない中間的な構造
・非常に不安定で、すぐに生成物または反応物に変化
・寿命は10⁻¹³秒程度
活性化エネルギーは、反応物から遷移状態までのエネルギー差として定義されます。
遷移状態が高エネルギーであるほど、活性化エネルギーは大きくなり、反応は遅くなるのです。
・反応が起こるために必要な最小エネルギー
・反応物から遷移状態までのエネルギー差
・Eaが大きいほど反応は遅い
・Eaが小さいほど反応は速い
活性化エネルギーの単位と記号
続いては、活性化エネルギーを表す単位と記号について確認していきましょう。
活性化エネルギーの単位
活性化エネルギーの単位は、エネルギーの単位です。
SI単位系ではJ/mol(ジュール毎モル)が標準的。
よく使われる単位:
・J/mol(ジュール毎モル):SI単位
・kJ/mol(キロジュール毎モル):最も一般的
・kcal/mol(キロカロリー毎モル):古い文献で使用
・eV(電子ボルト):物理化学や材料科学で使用
単位の換算:
1 eV = 96.485 kJ/mol
1 kJ/mol = 0.2390 kcal/mol
1 kJ/mol = 0.01036 eV
活性化エネルギーの典型的な範囲:
・非常に小さい:10〜30 kJ/mol(速い反応)
・小さい:30〜60 kJ/mol(比較的速い反応)
・中程度:60〜120 kJ/mol(中程度の速度)
・大きい:120〜200 kJ/mol(遅い反応)
・非常に大きい:200〜400 kJ/mol(非常に遅い反応)
活性化エネルギーとアレニウスの式
活性化エネルギーは、アレニウスの式に登場する重要なパラメータです。
アレニウスの式:
ここで、
・k:反応速度定数
・A:頻度因子(前指数因子)
・Ea:活性化エネルギー [J/mol]
・R:気体定数 = 8.314 J/(mol·K)
・T:絶対温度 [K]
この式は、反応速度定数kが活性化エネルギーEaと温度Tによってどう決まるかを表しています。
アレニウスの式から分かること:
・Eaが大きいほど、kは小さくなる(反応が遅い)
・Eaが小さいほど、kは大きくなる(反応が速い)
・温度Tが高いほど、kは大きくなる(反応が速い)
・Eaが大きいほど、温度依存性が強い
正反応と逆反応の活性化エネルギー
可逆反応では、正反応と逆反応それぞれに活性化エネルギーがあります。
・正反応の活性化エネルギー:Ea(正)
・逆反応の活性化エネルギー:Ea(逆)
これらの関係:
ここで、ΔHは反応熱
発熱反応(ΔH 0)の場合:
・Ea(正) > Ea(逆)
・逆反応の方が起こりやすい
| 記号 | 名称 | 単位 |
|---|---|---|
| Ea | 活性化エネルギー | kJ/mol |
| ΔH | 反応熱 | kJ/mol |
| k | 反応速度定数 | 様々(反応次数による) |
これらの関係を理解することが、化学反応の熱力学と速度論を結びつける鍵となります。
活性化エネルギーの求め方と計算方法
続いては、活性化エネルギーを実際に求める方法を見ていきましょう。
アレニウスプロットによる求め方
最も一般的な活性化エネルギーの求め方は、アレニウスプロットを使う方法です。
アレニウスの式の両辺の対数を取ると、
または、
ln(k) = ln(A) – (Ea/R) × (1/T)
この式は、y = mx + bという直線の式と同じ形。
・縦軸:ln(k)
・横軸:1/T
・傾き:-Ea/R
・切片:ln(A)
手順:
1. 異なる温度で反応速度定数kを測定する
2. 各温度について、ln(k)と1/Tを計算する
3. ln(k)を縦軸、1/Tを横軸としてプロットする
4. データ点を直線でフィッティングする
5. 傾きから活性化エネルギーを計算する
したがって、
Ea = -傾き × R
R = 8.314 J/(mol·K)を代入すれば、Eaが求まる。
ある反応で、次のデータが得られた。
・300 K:k = 1.0 × 10⁻⁴ s⁻¹
・320 K:k = 4.0 × 10⁻⁴ s⁻¹
・340 K:k = 1.5 × 10⁻³ s⁻¹
・360 K:k = 5.0 × 10⁻³ s⁻¹
各温度について、ln(k)と1/Tを計算:
・300 K:ln(k) = -9.21、1/T = 0.00333 K⁻¹
・320 K:ln(k) = -7.82、1/T = 0.00313 K⁻¹
・340 K:ln(k) = -6.50、1/T = 0.00294 K⁻¹
・360 K:ln(k) = -5.30、1/T = 0.00278 K⁻¹
これをプロットして直線フィッティングすると、
傾き ≈ -7000 K
Ea = -(-7000) × 8.314 = 58,200 J/mol ≈ 58 kJ/mol
活性化エネルギーは約58 kJ/mol。
2つの温度での測定から求める方法
2つの温度でのデータがあれば、直接計算できます。
これを変形すると、
Ea = R × ln(k₂/k₁) / (1/T₁ – 1/T₂)
ある反応の速度定数が、
・300 K:k₁ = 2.0 × 10⁻³ s⁻¹
・350 K:k₂ = 1.5 × 10⁻² s⁻¹
活性化エネルギーは?
Ea = R × ln(k₂/k₁) / (1/T₁ – 1/T₂)
= 8.314 × ln(1.5 × 10⁻² / 2.0 × 10⁻³) / (1/300 – 1/350)
= 8.314 × ln(7.5) / (0.003333 – 0.002857)
= 8.314 × 2.015 / 0.000476
= 35,200 J/mol ≈ 35 kJ/mol
活性化エネルギーは約35 kJ/mol。
温度係数Q10から求める方法
温度係数Q10(温度が10℃上昇したときの反応速度の比)が分かれば、活性化エネルギーを推定できます。
これを変形すると、
Ea = R × T² × ln(Q10) / 10
室温(25℃ = 298 K)でQ10 = 2.5の反応の活性化エネルギーは?
Ea = R × T² × ln(Q10) / 10
= 8.314 × (298)² × ln(2.5) / 10
= 8.314 × 88804 × 0.916 / 10
= 67,600 J/mol ≈ 68 kJ/mol
活性化エネルギーは約68 kJ/mol。
・アレニウスプロット:最も正確(複数温度での測定)
・2点法:簡便(2つの温度での測定)
・Q10法:推定(温度係数から)
・Ea = -傾き × R(アレニウスプロット)
・Ea = R × ln(k₂/k₁) / (1/T₁ – 1/T₂)(2点法)
これらの方法を使い分けることで、様々な状況で活性化エネルギーを求めることができるでしょう。
触媒・酵素と活性化エネルギー
続いては、触媒や酵素が活性化エネルギーに与える影響を見ていきましょう。
触媒の効果と活性化エネルギー
触媒(しょくばい、catalyst)とは、自身は変化せずに化学反応の速度を速める物質のことです。
触媒の働きの本質は、活性化エネルギーを下げること。
触媒がない場合:
・高い活性化エネルギー障壁
・反応が遅い
・高温が必要
触媒がある場合:
・低い活性化エネルギー障壁
・反応が速い
・低温でも進行
重要なポイント:
・触媒は活性化エネルギーを下げる
・反応熱(ΔH)は変わらない
・平衡定数も変わらない
・反応経路が変わる(別の遷移状態を経由)
触媒による活性化エネルギーの低下:
・通常:10〜100 kJ/mol程度の低下
・効果的な触媒:活性化エネルギーを1/2〜1/5に減少
2H₂O₂ → 2H₂O + O₂
・触媒なし:Ea ≈ 75 kJ/mol
・酸化マンガン(IV)触媒:Ea ≈ 50 kJ/mol
・白金触媒:Ea ≈ 49 kJ/mol
触媒により活性化エネルギーが約25 kJ/mol低下。
これにより、室温での反応速度は数百倍〜数千倍になる。
酵素と活性化エネルギー
酵素(こうそ、enzyme)は、生体内で働くタンパク質性の触媒です。
酵素は極めて高い触媒能力を持ち、活性化エネルギーを大幅に下げることができます。
酵素の特徴:
・基質特異性が高い(特定の反応だけを触媒)
・反応速度が非常に速い(10⁶〜10¹⁷倍の加速)
・温和な条件で機能(常温・常圧・中性pH)
・活性化エネルギーを大幅に下げる
酵素による活性化エネルギーの低下:
・通常の触媒:10〜50 kJ/mol程度の低下
・酵素:50〜100 kJ/mol以上の低下
CO(NH₂)₂ + H₂O → CO₂ + 2NH₃
・無触媒:Ea ≈ 134 kJ/mol(室温ではほぼ進行しない)
・ウレアーゼ(酵素):Ea ≈ 30 kJ/mol
酵素により活性化エネルギーが約100 kJ/mol低下。
反応速度は約10¹⁴倍に加速される。
温度依存性と触媒・酵素
触媒や酵素がある場合、温度依存性はどう変わるのでしょうか。
活性化エネルギーが下がると、温度依存性は弱くなります。
Eaが小さくなると、Q10も小さくなる。
具体例(室温付近):
・無触媒(Ea = 100 kJ/mol):Q10 ≈ 5
・触媒あり(Ea = 50 kJ/mol):Q10 ≈ 2
・酵素あり(Ea = 30 kJ/mol):Q10 ≈ 1.5
触媒や酵素を使うことで、温度を上げなくても反応を速く進めることができるのです。
酵素の温度特性:
・30〜40℃:最適温度(反応速度が最大)
・50℃以上:酵素が変性して活性低下
・0℃付近:活性は低いが安定
・活性化エネルギーを下げる
・反応速度を大幅に増加させる
・反応熱(ΔH)は変わらない
・温度依存性が弱くなる
・酵素は特に効果が大きい(Ea低下:50〜100 kJ/mol)
様々な反応の活性化エネルギー一覧(文献値)
続いては、代表的な化学反応や生化学反応の活性化エネルギーの文献値を確認していきましょう。
気相反応の活性化エネルギー
気相での化学反応の活性化エネルギーです。
分解反応:
・N₂O₅の分解:Ea ≈ 103 kJ/mol
・NO₂の分解:Ea ≈ 111 kJ/mol
・H₂O₂の分解:Ea ≈ 75 kJ/mol
・HI の分解:Ea ≈ 186 kJ/mol
合成反応:
・H₂ + I₂ → 2HI:Ea ≈ 167 kJ/mol
・H₂ + Cl₂ → 2HCl:Ea ≈ 23 kJ/mol(光反応)
・N₂ + O₂ → 2NO:Ea ≈ 315 kJ/mol(高温が必要)
燃焼反応:
・メタンの燃焼:Ea ≈ 125 kJ/mol
・プロパンの燃焼:Ea ≈ 115 kJ/mol
・水素の燃焼:Ea ≈ 40 kJ/mol
液相反応・有機反応の活性化エネルギー
液相や有機溶媒中での反応の活性化エネルギーです。
エステル化・加水分解:
・酢酸エチルの加水分解(酸触媒):Ea ≈ 50 kJ/mol
・酢酸エチルの加水分解(塩基触媒):Ea ≈ 42 kJ/mol
・ショ糖の反転(酸触媒):Ea ≈ 107 kJ/mol
置換反応:
・SN1反応:Ea ≈ 80〜120 kJ/mol
・SN2反応:Ea ≈ 60〜100 kJ/mol
重合反応:
・スチレンのラジカル重合:Ea ≈ 30〜40 kJ/mol
・エチレンの重合(触媒):Ea ≈ 40〜60 kJ/mol
酸化反応:
・グルコースの酸化:Ea ≈ 50〜80 kJ/mol
・アスコルビン酸の酸化:Ea ≈ 45〜55 kJ/mol
生化学反応・酵素反応の活性化エネルギー
酵素が関与する生化学反応の活性化エネルギーです。
加水分解酵素:
・ウレアーゼ(尿素分解):Ea ≈ 30 kJ/mol
・アミラーゼ(でんぷん分解):Ea ≈ 40〜50 kJ/mol
・ペプシン(タンパク質分解):Ea ≈ 35〜45 kJ/mol
・リパーゼ(脂質分解):Ea ≈ 25〜35 kJ/mol
酸化還元酵素:
・カタラーゼ(H₂O₂分解):Ea ≈ 8〜15 kJ/mol
・ペルオキシダーゼ:Ea ≈ 10〜20 kJ/mol
・デヒドロゲナーゼ:Ea ≈ 30〜50 kJ/mol
その他の酵素:
・DNA ポリメラーゼ:Ea ≈ 60〜80 kJ/mol
・リボソーム(タンパク質合成):Ea ≈ 40〜60 kJ/mol
・ATPase:Ea ≈ 50〜70 kJ/mol
酵素反応の活性化エネルギーは、無触媒反応に比べて50〜100 kJ/mol程度低いのが特徴です。
材料劣化・物理過程の活性化エネルギー
材料の劣化や物理的過程の活性化エネルギーです。
高分子の劣化:
・ポリエチレンの酸化劣化:Ea ≈ 80〜120 kJ/mol
・ポリプロピレンの熱劣化:Ea ≈ 100〜150 kJ/mol
・PVCの脱塩化水素:Ea ≈ 120〜140 kJ/mol
拡散過程:
・気体中の拡散:Ea ≈ 5〜20 kJ/mol
・液体中の拡散:Ea ≈ 15〜40 kJ/mol
・固体中の拡散:Ea ≈ 80〜300 kJ/mol
食品の劣化:
・油脂の酸化:Ea ≈ 50〜80 kJ/mol
・ビタミンCの分解:Ea ≈ 60〜90 kJ/mol
・タンパク質の変性:Ea ≈ 200〜400 kJ/mol
・メイラード反応:Ea ≈ 80〜120 kJ/mol
微生物の増殖・死滅:
・細菌の増殖:Ea ≈ 60〜80 kJ/mol
・細菌の死滅(加熱):Ea ≈ 200〜500 kJ/mol
・胞子の死滅:Ea ≈ 250〜350 kJ/mol
| 反応・過程 | 活性化エネルギーEa | 特徴 |
|---|---|---|
| 気相拡散 | 5〜20 kJ/mol | 非常に速い |
| カタラーゼ反応 | 8〜15 kJ/mol | 酵素反応(極めて速い) |
| 液相拡散 | 15〜40 kJ/mol | 速い |
| ウレアーゼ反応 | 30 kJ/mol | 酵素反応(速い) |
| 酢酸エチル加水分解 | 42〜50 kJ/mol | 中程度 |
| 油脂の酸化 | 50〜80 kJ/mol | 食品劣化 |
| H₂O₂分解(無触媒) | 75 kJ/mol | やや遅い |
| ポリマー劣化 | 80〜150 kJ/mol | 材料の寿命 |
| 尿素分解(無触媒) | 134 kJ/mol | 遅い |
| 固体中の拡散 | 80〜300 kJ/mol | 非常に遅い |
| N₂ + O₂ → 2NO | 315 kJ/mol | 極めて遅い(高温必要) |
活性化エネルギーの値は、反応条件、触媒の有無、温度範囲などによって変わることがあります。
文献値として記載されている値は、標準的な条件での代表値と考えてください。
まとめ 活性化エネルギーの求め方や値一覧は(文献値)?【触媒やアレニウス・温度依存性や酵素など】
活性化エネルギーについて、基本的な定義から単位、求め方、触媒や酵素の効果、様々な反応の文献値まで詳しく解説してきました。
活性化エネルギーEaは、化学反応が起こるために必要な最小限のエネルギーであり、反応物から遷移状態までのエネルギー差として定義されます。
単位はkJ/molが一般的で、10〜400 kJ/mol程度の範囲にあります。
活性化エネルギーの求め方には、アレニウスプロット(最も正確)、2点法(簡便)、Q10法(推定)などがあり、ln(k)と1/Tをプロットした直線の傾きから求めることができるのです。
触媒はEaを10〜100 kJ/mol程度下げることで反応を加速し、酵素はさらに大きく50〜100 kJ/mol以上下げることで生体内での反応を可能にします。
様々な反応の活性化エネルギーは、気相反応(50〜300 kJ/mol)、液相反応(40〜150 kJ/mol)、酵素反応(8〜80 kJ/mol)、材料劣化(50〜400 kJ/mol)など、反応の種類によって大きく異なるでしょう。
化学、生化学、材料科学、食品科学など、多くの分野で活性化エネルギーの知識が不可欠です。
この記事で学んだ知識を使って、化学反応の理解を深めてください。