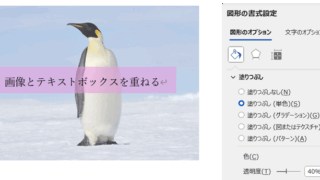金属製品の表面処理技術として古くから使われている「どぶづけメッキ」(溶融亜鉛めっき)について解説します。
この技術は鉄鋼製品の防食処理として広く利用されており、建築物や橋梁、電柱など私たちの身の回りの様々な場所で活躍しています。
電気めっきとの違いや、先メッキ、ユニクロメッキなどの関連技術と比較しながら、どぶづけメッキの特徴や利点について詳しく見ていきましょう。
ドブ漬けメッキとは?膜厚は?
それではまず、ドブ漬けメッキ(別名:溶融亜鉛めっき)とは何か、その膜厚についても解説していきます。
ドブ漬けメッキとは、鉄鋼製品を溶けた亜鉛の浴槽に浸漬させることで、表面に亜鉛の層を形成させる表面処理方法です。
「ドブ漬け」という名前の由来は、文字通り溶融した亜鉛の槽(ドブ)に製品を漬けることから来ています。
この方法は英語では「Hot-dip galvanizing」と呼ばれ、亜鉛の融点である約420℃前後の高温で行われます。
一般的に40〜150μm(ミクロン)の膜厚を得ることができ、これは電気めっきの5〜20μmと比較して非常に厚いのが特徴です。
ドブ漬けメッキの工程は、前処理(脱脂、酸洗い、フラックス処理)、めっき処理(溶融亜鉛浸漬)、後処理(冷却、検査)の順で行われます。
前処理では鉄鋼表面の油脂や酸化物を除去し、フラックス処理で亜鉛との密着性を高めます。
めっき処理では、約450〜470℃の溶融亜鉛浴に鉄鋼製品を浸漬させ、表面に亜鉛層を形成させます。
この際、鉄と亜鉛の間には合金層(Fe-Zn層)が形成され、その上に純亜鉛層が形成されるという層構造になります。
膜厚は浸漬時間や引き上げ速度、鋼材の形状や成分によって変化しますが、JIS規格(JIS H 8641)では、HDZ35(平均膜厚35μm以上)、HDZ40(平均膜厚40μm以上)、HDZ45(平均膜厚45μm以上)などのように規定されています。
ドブ漬けメッキの表面は、施工直後は銀白色の光沢を持ちますが、時間の経過とともに亜鉛が酸化して灰色に変化します。
ドブ漬けメッキと電気めっきの違いは?
続いては、ドブ漬けメッキと電気めっきの違いについて確認していきます。
両者は金属表面に別の金属を被覆する点では同じですが、その方法や特性には大きな違いがあります。
まず、形成方法の違いがあります。ドブ漬けメッキは溶融した亜鉛に製品を浸漬させる物理的な方法であるのに対し、電気めっきは電気分解を利用して金属イオンを析出させる電気化学的な方法です。
ドブ漬けメッキは通常40〜150μmと厚い膜を形成できますが、電気めっきは一般的に5〜20μmと薄い膜になります。
この膜厚の違いが、耐食性や耐久性に大きく影響します。
処理温度も大きく異なります。ドブ漬けメッキは亜鉛の融点以上(約450℃)の高温で行われるのに対し、電気めっきは常温〜60℃程度の比較的低温で行われます。
対応可能な形状にも違いがあります。ドブ漬けメッキは浸漬できるサイズの制限があり、細かい穴や隙間にも均一にめっきできますが、形状によっては亜鉛が溜まって厚くなる部分が生じることがあります。
一方、電気めっきは電流密度の影響を受けるため、複雑な形状の製品では均一なめっき厚さを得るのが難しい場合があります。
耐食性については、ドブ漬けメッキは厚い亜鉛層と合金層があるため、長期間の防食効果が期待できます。亜鉛は鉄よりもイオン化傾向が大きいため、犠牲防食効果も発揮します。
電気めっきは膜が薄いため、耐久性はドブ漬けメッキより劣りますが、表面の美観や精密さが求められる用途に適しています。
コストと環境負荷についても違いがあり、ドブ漬けメッキは設備投資が大きく、高温処理のためエネルギー消費が多いですが、電気めっきは廃液処理などの環境対策コストがかかります。
ドブ漬けメッキと先メッキ、ユニクロメッキとの違いは?
続いては、ドブ漬けメッキと先メッキ、ユニクロメッキとの違いについて確認していきます。
まず、「先メッキ」(溶融亜鉛めっき鋼板)とは、鋼板を連続的に溶融亜鉛めっき処理する方法で、一般にガルバリウム鋼板などとして知られています。
先メッキとドブ漬けメッキの最大の違いは、処理対象と製造プロセスにあります。先メッキは鋼板の段階で連続的にめっき処理を行い、その後に加工する「後加工」方式です。
一方、ドブ漬けメッキは製品形状に加工した後にめっき処理を行う「後メッキ」方式です。
そのため、加工性に優れていますが、耐食性はドブ漬けメッキよりも低くなります。
次に「ユニクロメッキ」(電気亜鉛めっき)についてですが、これは電気めっき法を用いて亜鉛めっきを施す方法です。
ユニクロメッキは電気めっきの一種で、溶融亜鉛めっきではなく、常温の亜鉛溶液中で電気分解により亜鉛を析出させます。
ユニクロメッキの膜厚は一般的に5〜20μm程度と非常に薄く、ドブ漬けメッキと比較すると耐食性は低いですが、表面の美観や寸法精度が良いという特徴があります。
また、ユニクロメッキは低温処理のため、熱による鋼材の変形が少なく、精密な部品や熱に弱い材料にも適用できます。
用途としては、ドブ漬けメッキは橋梁や鉄塔、ガードレールなど屋外で長期間使用される構造物に適しています。
先メッキは建築用の屋根材や壁材、自動車部品などに、ユニクロメッキは屋内で使用される部品や美観が重要な部品などに使用されることが多いです。
選定基準としては、要求される耐食性、使用環境、コスト、外観、加工性などを考慮して適切な方法を選ぶことが重要です。
特に腐食環境が厳しい場所では耐食性に優れたドブ漬けメッキが、見た目が重要な部分では美観に優れた電気めっきが選ばれることが多いです。
このように、ドブ漬けメッキ、先メッキ、ユニクロメッキはそれぞれ特性が異なるため、用途に応じて適切な方法を選択することが大切です。
まとめ どぶづけメッキとは?電気メッキやユニクロメッキ等との違いは?
この記事では、どぶづけメッキとは?厚みや電気メッキとの違いは?先メッキ・ユニクロメッキ等ともについて解説しました。
科学に関する用語を理解しさらに科学技術の発展に役立てていただければ幸いです。