化学や物理の授業でエントロピーという言葉を聞いて、難しいと感じたことはありませんか。抽象的な概念で、公式も複数あり、計算方法もわかりにくいと悩んでいる方も多いはずです。しかし、エントロピーは熱力学を理解する上で欠かせない重要な概念です。
実は、エントロピーの基本的な定義や公式、計算方法を順を追って学べば、決して難しくありません。この記事では、エントロピーの定義から単位、様々な公式、具体的な求め方、エントロピー変化の意味まで、わかりやすく丁寧に解説していきます。
計算例も交えながら実践的に学べる内容になっていますので、エントロピーが苦手な方、テスト対策をしたい方は、ぜひ最後までお読みください。この記事を読めば、エントロピーの意味がわからないという悩みを解決できるはずです。
エントロピーとは?基本的な定義と意味
それではまず、エントロピーの基本的な定義と意味について解説していきます。
エントロピーの定義
エントロピーとは、物質や系の乱雑さ、無秩序さの程度を表す物理量です。記号ではSで表され、thermodynamic entropy(熱力学的エントロピー)とも呼ばれます。
より厳密に言えば、エントロピーは系がとり得る微視的状態の数に関係する量です。同じ巨視的状態でも、分子レベルで見ると様々な配置パターンがあり、そのパターンが多いほどエントロピーは大きくなります。
歴史的には、19世紀にクラウジウスが熱力学の研究から導入した概念です。その後、ボルツマンが統計力学的な解釈を与え、エントロピーの本質が明らかになりました。
エントロピーは状態量と呼ばれる物理量の一つで、系の現在の状態だけで決まり、そこに至る過程には依存しません。温度、圧力、物質の量が決まれば、エントロピーの値も一意に決まります。
エントロピーの単位
エントロピーの単位は、国際単位系(SI単位系)ではJ/K(ジュール毎ケルビン)が使われます。これは、エネルギーの単位であるジュールを、温度の単位であるケルビンで割った単位です。
化学の分野では、物質量あたりのエントロピーを扱うことが多いため、J/(mol·K)またはJ·K⁻¹·mol⁻¹という単位がよく使われます。これは1モルあたりのエントロピーを表しています。
また、キロジュールを使ってkJ/(mol·K)と表記することもあります。1 kJ/(mol·K) = 1000 J/(mol·K)の関係があります。
| 単位 | 読み方 | 使用場面 |
|---|---|---|
| J/K | ジュール毎ケルビン | 物理学、全エントロピー |
| J/(mol·K) | ジュール毎モル毎ケルビン | 化学、モルエントロピー |
| kJ/(mol·K) | キロジュール毎モル毎ケルビン | 化学、大きな値を扱うとき |
| cal/(mol·K) | カロリー毎モル毎ケルビン | 古い文献 |
単位を見れば、エントロピーが熱エネルギーと温度に関係した量であることがわかります。問題を解く際には、単位を正しく扱うことが重要です。
エントロピーが表すもの
エントロピーが具体的に何を表しているのか、イメージを持つことが理解への第一歩です。
エントロピーは「乱雑さ」や「無秩序さ」を表すと説明されますが、より正確には系のとり得る状態の多様性を表しています。状態の選択肢が多いほど、エントロピーは大きくなります。
気体は分子が自由に動き回れるため、とり得る配置が非常に多く、エントロピーが大きい状態です。液体は気体よりも配置が制限され、固体はさらに制限されるため、気体>液体>固体の順でエントロピーは小さくなります。
温度が上がると分子の運動が激しくなり、とり得る状態が増えるため、エントロピーは増加します。また、物質の量が増えれば、それだけ配置のパターンも増えるため、エントロピーも増加します。
気体>液体>固体
高温>低温
大量>少量
複雑な分子>単純な分子
化学反応では、生成物と反応物のエントロピーの差が、反応の自発性を決める重要な要素の一つとなります。
エントロピーの公式と数式表現
続いては、エントロピーを表す様々な公式と数式について確認していきます。
熱力学的定義式
エントロピーの最も基本的な熱力学的定義は、クラウジウスによって与えられました。
可逆過程において、微小な熱量dQが温度Tで系に加えられるとき、エントロピー変化dSは次の式で定義されます。
dS = dQ/T
この式が、エントロピーの熱力学的定義の基礎となります。ここで、dQは可逆的に加えられた熱量、Tは絶対温度(ケルビン)です。
有限の変化に対しては、積分形で表されます。
ΔS = ∫(dQ/T)
この式から、同じ熱量でも低温で加えられた方がエントロピー変化が大きいことがわかります。例えば、100Jの熱量を100Kで加えた場合のエントロピー変化は、300Kで加えた場合の3倍になります。
定温過程(温度が一定)の場合、積分が簡単になり、次のように表せます。
ΔS = Q/T
この式は、定温での可逆過程におけるエントロピー変化を計算する際によく使われます。
ボルツマンの式
エントロピーの統計力学的な定義は、ボルツマンによって与えられました。これはエントロピーの微視的な意味を明確にする重要な式です。
S = k ln W
ここで、kはボルツマン定数(1.38×10⁻²³ J/K)、Wは系がとり得る微視的状態の数です。lnは自然対数を表します。
この式は、エントロピーが状態数の対数に比例することを示しています。状態数が多いほど、つまり乱雑な状態ほど、エントロピーは大きくなります。
例えば、2つの区別できる粒子A、Bを2つの箱に入れる場合を考えます。とり得る状態は、(両方左、両方右、Aが左でBが右、Aが右でBが左)の4通りです。したがって、W = 4となり、S = k ln 4 = k ln 2² = 2k ln 2となります。
ボルツマンの式は、マクロな熱力学的量であるエントロピーと、ミクロな統計的量である状態数を結びつける画期的な式でした。この式はボルツマンの墓石にも刻まれています。
エントロピー変化の式
化学反応におけるエントロピー変化を計算する式は、エンタルピー変化の式と似た形をしています。
反応のエントロピー変化ΔSは、次の式で計算されます。
ΔS = Σ(生成物のエントロピー) − Σ(反応物のエントロピー)
より正確には、標準状態でのモルエントロピーS°を使って、
ΔS° = ΣnS°(生成物) − ΣmS°(反応物)
と表されます。ここで、n、mは化学反応式の係数です。
また、理想気体の等温膨張におけるエントロピー変化は、次の式で表されます。
ΔS = nR ln(V₂/V₁) = nR ln(P₁/P₂)
ここで、nは物質量、Rは気体定数(8.31 J/(mol·K))、V₁、V₂は体積、P₁、P₂は圧力です。
定圧での加熱によるエントロピー変化は、
ΔS = nCp ln(T₂/T₁)
で表されます。Cpはモル定圧熱容量です。
| 過程 | エントロピー変化の式 |
|---|---|
| 定温可逆過程 | ΔS = Q/T |
| 理想気体の等温膨張 | ΔS = nR ln(V₂/V₁) |
| 定圧加熱 | ΔS = nCp ln(T₂/T₁) |
| 化学反応 | ΔS° = ΣnS°(生成物) − ΣmS°(反応物) |
これらの式を状況に応じて使い分けることで、様々な過程でのエントロピー変化を計算できます。
エントロピーの求め方と計算方法
続いては、エントロピーを実際に求める具体的な計算方法を見ていきます。
熱力学的な計算方法
熱力学的な方法でエントロピー変化を求める基本的な手順を説明します。
定温可逆過程の場合、ΔS = Q/Tの式を使います。例えば、300Kで600Jの熱量を可逆的に吸収した場合、
ΔS = 600 J / 300 K = 2 J/K
となります。単位に注意しながら計算することが重要です。
温度が変化する場合は、積分を使います。定圧でn molの物質を温度T₁からT₂まで加熱する場合、
ΔS = nCp ln(T₂/T₁)
を使います。例えば、1 molの水(Cp = 75.3 J/(mol·K))を300Kから350Kまで加熱する場合、
ΔS = 1 mol × 75.3 J/(mol·K) × ln(350/300)
= 75.3 × ln(1.167)
= 75.3 × 0.154
= 11.6 J/K
となります。
理想気体の等温膨張では、ΔS = nR ln(V₂/V₁)を使います。1 molの理想気体が300Kで10Lから20Lに膨張する場合、
ΔS = 1 mol × 8.31 J/(mol·K) × ln(20/10)
= 8.31 × ln(2)
= 8.31 × 0.693
= 5.76 J/K
となります。
標準エントロピーを使った計算
化学反応のエントロピー変化を求める最も一般的な方法は、標準モルエントロピーS°を使う方法です。
標準モルエントロピーとは、標準状態(25℃、1 atm)における1 molあたりのエントロピーで、物質ごとに表にまとめられています。
反応のエントロピー変化は、
ΔS° = ΣnS°(生成物) − ΣmS°(反応物)
で計算されます。
例として、水素と酸素から水が生成する反応を考えます。
2H₂(気) + O₂(気) → 2H₂O(液)
各物質の標準モルエントロピーは次の通りです。
H₂(気):130.7 J/(mol·K)
O₂(気):205.2 J/(mol·K)
H₂O(液):69.9 J/(mol·K)
これらを式に代入すると、
ΔS° = 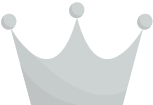 −
− 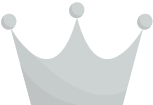
= 139.8 − [261.4 + 205.2]
= 139.8 − 466.6
= −326.8 J/K
1. 係数を必ず掛ける
2. 生成物から反応物を引く順序を守る
3. 単位を揃える
4. 気体、液体、固体の違いに注意
この反応では気体が減って液体になるため、エントロピーは減少します(ΔS°<0)。これは気体の方が液体よりも乱雑な状態だからです。
具体的な計算例と問題演習
実際の問題を通して、エントロピーの計算方法を確認しましょう。
計算例1:相転移のエントロピー変化
水1 molが100℃、1 atmで液体から気体に変化するとき、蒸発熱は40.7 kJ/molです。このときのエントロピー変化を求めてください。
解答:定温での相転移なので、ΔS = Q/Tを使います。
T = 100℃ = 373 K
Q = 40.7 kJ/mol = 40700 J/mol
ΔS = 40700 J/mol / 373 K = 109 J/(mol·K)
水が蒸発すると、エントロピーは大きく増加します。
計算例2:化学反応のエントロピー変化
次の反応の標準エントロピー変化を求めてください。
N₂(気) + 3H₂(気) → 2NH₃(気)
標準モルエントロピー:
N₂(気):191.6 J/(mol·K)
H₂(気):130.7 J/(mol·K)
NH₃(気):192.8 J/(mol·K)
解答:
ΔS° = 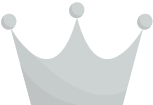 −
− 
= 385.6 − [191.6 + 392.1]
= 385.6 − 583.7
= −198.1 J/K
4分子の気体から2分子の気体ができるため、エントロピーは減少します。
計算例3:混合のエントロピー
2種類の理想気体が混合するとき、混合のエントロピー増加は次の式で表されます。
ΔS混合 = −R(n₁ ln x₁ + n₂ ln x₂)
ここで、n₁、n₂は各気体の物質量、x₁、x₂はモル分率です。
1 molのN₂と1 molのO₂を混合する場合、
x₁ = x₂ = 0.5
ΔS混合 = −8.31 × (1 × ln 0.5 + 1 × ln 0.5)
= −8.31 × 2 × (−0.693)
= 11.5 J/K
混合により、エントロピーは必ず増加します。
エントロピー変化とその意味を理解する
続いては、エントロピー変化が何を意味するのかを詳しく確認していきます。
エントロピー変化ΔSとは
エントロピー変化ΔSは、過程の前後でエントロピーがどれだけ変化したかを表す量です。
ΔS = S(終状態) − S(始状態)
という定義式で表されます。エンタルピー変化ΔHと同様の考え方です。
エントロピー変化は、反応や過程の自発性を判断する上で重要な役割を果たします。ギブズの自由エネルギー変化ΔGは、
ΔG = ΔH − TΔS
という式で表され、ΔG<0のとき反応は自発的に進みます。この式から、エントロピー変化が大きいほど、反応は自発的に進みやすいことがわかります。
特に高温では、TΔSの項が大きくなるため、エントロピー変化の影響が支配的になります。これが、高温で吸熱反応でも自発的に進む理由です。
エントロピー変化を理解することは、化学平衡や反応速度論を学ぶ上でも欠かせません。
正負の意味と判断方法
エントロピー変化の正負は、過程の性質を表す重要な情報です。
ΔS>0(正)の場合、エントロピーが増加しており、系がより乱雑な状態になったことを意味します。孤立系では自発的に進む方向です。
具体例:
固体→液体→気体(相転移)
膨張(体積の増加)
溶解(固体が溶ける)
分子数が増える反応
ΔS<0(負)の場合、エントロピーが減少しており、系がより秩序だった状態になったことを意味します。孤立系では自発的には進みません。
具体例:
気体→液体→固体(相転移)
圧縮(体積の減少)
結晶化(溶質が析出)
分子数が減る反応
| 変化の種類 | ΔSの符号 | 理由 |
|---|---|---|
| 固体→気体 | 正(+) | 分子の自由度が増加 |
| 気体→固体 | 負(−) | 分子の自由度が減少 |
| 溶解 | 正(+) | 粒子が拡散 |
| 2A → A₂ | 負(−) | 分子数が減少 |
| A₂ → 2A | 正(+) | 分子数が増加 |
エントロピー変化の符号を素早く判断できるようになると、反応の自発性の予測が容易になります。
化学反応でのエントロピー変化
化学反応におけるエントロピー変化の傾向を理解しておくことは、化学の理解を深める上で重要です。
気体の分子数が変化する反応では、エントロピー変化が大きくなります。気体は液体や固体に比べてエントロピーが非常に大きいためです。
例えば、CaCO₃(固) → CaO(固) + CO₂(気)という反応では、固体から気体が発生するため、大きな正のエントロピー変化があります。
逆に、N₂(気) + 3H₂(気) → 2NH₃(気)のように気体分子数が減少する反応では、エントロピーは減少します(ΔS<0)。
気体分子数が増える → ΔS>0
気体分子数が減る → ΔS<0
固体や液体が気体になる → ΔS>0(大)
気体が固体や液体になる → ΔS<0(大)
温度の影響も重要です。温度が上がると、すべての物質のエントロピーは増加します。これは分子の運動エネルギーが増え、とり得る状態が増えるためです。
圧力の影響では、圧力が上がると気体のエントロピーは減少します。体積が減って分子の配置の選択肢が減るためです。
これらの傾向を理解しておくことで、計算する前にエントロピー変化の符号や大きさを予測できるようになります。予測と計算結果を照合することで、計算ミスにも気づきやすくなります。
まとめ エントロピーの定義や計算方法!意味がわからないを解決!
エントロピーの定義、単位、公式、求め方、エントロピー変化について詳しく解説してきました。
エントロピーは物質や系の乱雑さを表す物理量で、単位にはJ/KやJ/(mol·K)が使われます。熱力学的定義式dS = dQ/Tと、統計力学的なボルツマンの式S = k ln Wという2つの重要な公式があります。
エントロピー変化の計算方法には、熱力学的な方法と標準エントロピーを使う方法があり、状況に応じて使い分けます。ΔS = ΣS°(生成物) − ΣS°(反応物)という式は、化学反応での計算に頻繁に使われます。
エントロピー変化ΔSの正負は、系の乱雑さの増減を表します。ΔS>0なら乱雑さが増加、ΔS<0なら減少です。気体の生成や分子数の増加はエントロピーを増やし、その逆は減らす傾向があります。
エントロピーは熱力学第二法則と密接に関係し、反応の自発性を決める重要な因子です。ギブズエネルギーの式ΔG = ΔH − TΔSにおいて、エントロピー項が反応の方向を決定します。
この記事で学んだ知識を使って、ぜひエントロピーの計算問題に挑戦してみてください。定義と公式をしっかり理解すれば、エントロピーは決して難しくありません。





