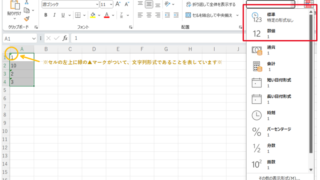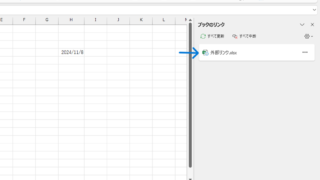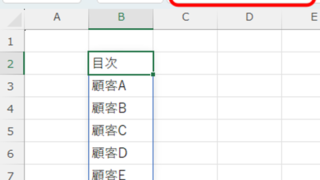熱力学や工学の分野で頻繁に登場する「比エンタルピー」という概念は、エネルギーの流れを理解する上で非常に重要な物理量です。冷凍機やボイラー、タービンなどの熱機器の設計や性能評価には欠かせない指標となっています。
比エンタルピーとは、物質単位質量あたりのエンタルピーを表す状態量であり、物質がどれだけのエネルギーを持っているかを示す重要な指標です。エンタルピーという言葉自体は聞き慣れないかもしれませんが、実は私たちの身の回りにある様々な機器で、この概念が活用されています。
本記事では、比エンタルピーの基本的な定義から、単位や計算方法、そして実際の工学分野での使い方まで、わかりやすく詳しく解説していきます。熱力学を学び始めた方や、実務で比エンタルピーを扱う必要がある方に役立つ内容となっています。
比エンタルピーとは?基本的な定義と概念
それではまず、比エンタルピーの基本的な定義と概念について解説していきます。
比エンタルピーの定義と物理的意味
比エンタルピーは、単位質量あたりのエンタルピーを表す物理量であり、記号では小文字のhで表記されます。エンタルピーそのものが大文字のHで表されるのに対し、比エンタルピーは質量で割った値となります。
数式で表すと、比エンタルピーhは以下のように定義されます。
h = H / m
ここで、Hは全体のエンタルピー、mは質量を表します。
物理的な意味としては、比エンタルピーは物質が持つ内部エネルギーと、その物質が周囲に対して仕事をする能力を合わせた量を、単位質量あたりで表したものです。より具体的には、物質の温度、圧力、相状態によって決まる固有の値となります。
エンタルピー自体は、内部エネルギーUに圧力Pと体積Vの積を加えたものとして定義されます。
H = U + PV
この関係から、比エンタルピーは次のように表現することもできます。
h = u + Pv
ここで、uは比内部エネルギー、vは比体積(単位質量あたりの体積)を表します。
エンタルピーと比エンタルピーの違い
エンタルピーと比エンタルピーの違いを明確に理解することは、熱力学計算において非常に重要です。
エンタルピーHは、系全体が持つ総エネルギー量を表す示量性状態量です。示量性とは、系の大きさ(質量や物質量)に比例する性質のことで、質量が2倍になればエンタルピーも2倍になります。単位はジュール(J)で表されます。
一方、比エンタルピーhは、単位質量あたりのエンタルピーを表す示強性状態量です。示強性とは、系の大きさによらず一定の値を持つ性質のことで、物質の状態(温度、圧力、相)が同じであれば、質量に関係なく同じ値となります。
| 項目 | エンタルピー(H) | 比エンタルピー(h) |
|---|---|---|
| 性質 | 示量性状態量 | 示強性状態量 |
| 質量依存性 | 質量に比例する | 質量に依存しない |
| 単位 | J(ジュール) | J/kg(ジュール毎キログラム) |
| 用途 | 系全体のエネルギー評価 | 物質の状態の評価、流量計算 |
実際の工学計算では、比エンタルピーを使用することが圧倒的に多くなります。なぜなら、流体の状態は温度と圧力で決まり、質量によらず一定の比エンタルピー値を持つためです。蒸気表などの物性値表も、比エンタルピーで記載されています。
1kgの水蒸気の比エンタルピーは約2676 kJ/kgです。
もし5kgの水蒸気があれば、全体のエンタルピーHは、H = 5 kg × 2676 kJ/kg = 13,380 kJ となります。
しかし、比エンタルピーhは質量によらず2676 kJ/kgのまま変わりません。これが示強性と示量性の違いです。
熱力学における比エンタルピーの役割
熱力学において、比エンタルピーは特に定常流れ系のエネルギー保存則を表す際に中心的な役割を果たします。
熱力学第一法則を定常流れ系に適用すると、入口と出口での比エンタルピーの差が、その系で行われる仕事や熱のやり取りと直接関係します。これを定常流れエネルギー式(SFEE: Steady Flow Energy Equation)と呼びます。
基本的な形は以下のようになります。
q – w = h₂ – h₁ + (v₂² – v₁²)/2 + g(z₂ – z₁)
ここで、qは単位質量あたりの入熱、wは単位質量あたりの仕事、v₁、v₂は入口と出口の流速、z₁、z₂は高さを表します。
多くの実際の機器では、運動エネルギーや位置エネルギーの変化が比エンタルピー変化に比べて無視できるほど小さいため、式は簡略化されます。
q – w = h₂ – h₁
この関係式により、比エンタルピーの変化を知ることで、機器で行われる仕事量や必要な熱量を直接計算できるのです。
タービンでは、高温高圧の蒸気が持つ比エンタルピーが、低温低圧になることで減少し、その差が仕事として取り出されます。逆にコンプレッサーでは、仕事を加えることで流体の比エンタルピーが増加します。
熱交換器では、高温流体の比エンタルピー減少量と低温流体の比エンタルピー増加量が等しくなることを利用して、伝熱量を計算します。このように、比エンタルピーは様々な熱機器の設計と性能評価の基礎となっています。
比エンタルピーの単位と表記方法
続いては、比エンタルピーの単位と表記方法を確認していきます。
SI単位系における比エンタルピーの単位
SI単位系(国際単位系)において、比エンタルピーの基本単位はJ/kg(ジュール毎キログラム)です。これは、1キログラムあたりのエネルギーをジュールで表したものです。
ただし、実務では値が非常に大きくなることが多いため、kJ/kg(キロジュール毎キログラム)が最も一般的に使用されます。1 kJ/kg = 1000 J/kgの関係があります。
場合によっては、MJ/kg(メガジュール毎キログラム)が使用されることもあります。1 MJ/kg = 1000 kJ/kg = 1,000,000 J/kgとなります。
| 単位 | 記号 | 換算 | 使用場面 |
|---|---|---|---|
| ジュール毎キログラム | J/kg | 基本単位 | 理論計算 |
| キロジュール毎キログラム | kJ/kg | 1000 J/kg | 蒸気表、実務計算(最も一般的) |
| メガジュール毎キログラム | MJ/kg | 1000 kJ/kg | 燃料の発熱量表示 |
また、モル単位で表す場合は、J/mol(ジュール毎モル)やkJ/mol(キロジュール毎モル)が使用されます。これはモル比エンタルピーと呼ばれ、化学反応の計算などで用いられます。
質量基準の比エンタルピーとモル基準の比エンタルピーは、分子量Mを用いて以下のように変換できます。
h[kJ/kg] = h[kJ/mol] / M[kg/mol]
これを他の単位で表すと次のようになります。
2676 kJ/kg = 2,676,000 J/kg = 2.676 MJ/kg
水の分子量は約18 g/mol = 0.018 kg/molなので、モル基準では約48.2 kJ/molとなります。
工学単位系とその換算方法
SI単位系以外にも、地域や業界によって異なる単位系が使用されることがあります。特に北米では、ヤードポンド法に基づく単位が今でも広く使われています。
工学単位系での比エンタルピーの主な単位は、Btu/lb(英国熱量単位毎ポンド)です。Btuは British Thermal Unit の略で、1ポンドの水の温度を1°F上昇させるのに必要な熱量として定義されています。
主要な単位換算を以下にまとめます。
| 変換元 | 変換先 | 換算係数 |
|---|---|---|
| 1 kJ/kg | Btu/lb | 0.4299 Btu/lb |
| 1 Btu/lb | kJ/kg | 2.326 kJ/kg |
| 1 kcal/kg | kJ/kg | 4.184 kJ/kg |
| 1 kJ/kg | kcal/kg | 0.2388 kcal/kg |
日本では以前、カロリー単位系でkcal/kg(キロカロリー毎キログラム)が使用されていましたが、現在はSI単位のkJ/kgが標準となっています。ただし、古い文献や一部の業界では今でもkcal/kgが使用されることがあります。
温度・圧力との関係と状態量としての特性
比エンタルピーは状態量であり、物質の状態が決まれば一意に定まる値です。純粋な物質の場合、状態を決定するには通常2つの独立変数が必要となります。
最も一般的な独立変数の組み合わせは、温度Tと圧力Pです。つまり、ある物質の温度と圧力が与えられれば、その物質の比エンタルピーが決まります。
h = h(T, P)
ただし、この関係は物質の相状態によって異なります。気相(気体)、液相(液体)、そして両者が共存する気液二相状態では、それぞれ異なる関係式や表が必要です。
理想気体の場合、比エンタルピーは温度のみの関数となり、圧力には依存しません。
h = h(T) (理想気体の場合)
これは理想気体の重要な性質の一つです。
実在気体や液体の場合は、圧力の影響も考慮する必要があります。特に高圧下では、圧力による比エンタルピーの変化が無視できなくなります。
飽和液(沸騰直前の液体)の比エンタルピー:約419 kJ/kg
飽和蒸気(沸騰直後の蒸気)の比エンタルピー:約2676 kJ/kg
同じ温度でも、液相と気相では比エンタルピーが大きく異なります。この差が蒸発潜熱に相当し、約2257 kJ/kgとなります。
一方、100℃、10気圧の場合、飽和温度は約180℃まで上昇し、比エンタルピーの値も変化します。このように、温度と圧力の両方が比エンタルピーを決定します。
比エンタルピーは連続的に変化する量ですが、相変化が起こる場合は不連続な変化を示します。固体から液体へ、液体から気体への相変化では、温度が一定のまま比エンタルピーが大きく変化します。
比エンタルピーの計算方法と求め方
続いては、比エンタルピーの具体的な計算方法と求め方を確認していきます。
基本的な計算式と導出過程
比エンタルピーを計算する基本的な方法は、物質の状態や条件によって異なりますが、いくつかの代表的な計算式があります。
理想気体の場合、比エンタルピーは定圧比熱を用いて計算できます。
h = h₀ + ∫Cp dT
ここで、h₀は基準状態での比エンタルピー、Cpは定圧比熱、Tは温度です。
定圧比熱が温度によらず一定とみなせる場合(多くの実用計算ではこの仮定が成り立ちます)、式は簡単になります。
h₂ – h₁ = Cp(T₂ – T₁)
この式は、温度変化による比エンタルピー変化を計算する最も基本的な式です。
空気の定圧比熱:Cp ≈ 1.005 kJ/(kg・K)
温度変化:ΔT = 100℃ – 20℃ = 80 K
比エンタルピー変化:Δh = 1.005 × 80 = 80.4 kJ/kg
したがって、空気1kgあたり約80.4 kJのエネルギーが必要となります。
液体の場合も、同様に定圧比熱を用いた計算が可能です。ただし、液体の比熱は気体に比べて大きく、また温度や圧力による変化も考慮が必要な場合があります。
h = href + Cp,liquid(T – Tref)
ここで、hrefは基準温度Trefでの比エンタルピーです。
相変化を伴う場合は、潜熱を加える必要があります。
h = hliquid + hfg
ここで、hfgは蒸発潜熱(気化熱)を表します。
蒸気表や線図を用いた求め方
実際の工学計算では、理論式による計算よりも、蒸気表(Steam Tables)やモリエル線図などの物性値表・線図を用いる方法が一般的です。これらには実験的に求められた正確な値が記載されており、実在気体の挙動を正確に表現しています。
蒸気表は、水蒸気の温度、圧力、比エンタルピー、比体積、比エントロピーなどの関係をまとめた表です。飽和状態(液体と蒸気が共存する状態)の表と、過熱蒸気(飽和温度以上の蒸気)の表に分かれています。
蒸気表の使い方の基本手順は以下の通りです。
1. 既知の状態量(温度、圧力など)から該当する行を見つける
2. その行から比エンタルピーhの値を読み取る
3. 必要に応じて、飽和液hfと飽和蒸気hgの値を使って計算する
| 温度[℃] | 圧力[MPa] | 飽和液 hf[kJ/kg] | 蒸発潜熱 hfg[kJ/kg] | 飽和蒸気 hg[kJ/kg] |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0.1013 | 419.0 | 2257.0 | 2676.0 |
| 150 | 0.4758 | 632.2 | 2114.3 | 2746.5 |
| 200 | 1.5538 | 852.4 | 1940.8 | 2793.2 |
湿り蒸気(液体と蒸気が混在した状態)の比エンタルピーは、乾き度xを用いて計算します。
h = hf + x・hfg = (1-x)hf + x・hg
ここで、x(0≦x≦1)は質量基準の蒸気の割合を表します。
等温線、等圧線、乾き度の線などが描かれており、2つの状態量が分かれば、線図上の点を特定して比エンタルピーを読み取ることができます。特に冷凍サイクルやランキンサイクルの解析には欠かせません。
理想気体と実在気体における計算の違い
理想気体と実在気体では、比エンタルピーの計算方法に重要な違いがあります。
理想気体の場合、前述の通り比エンタルピーは温度のみの関数であり、圧力には依存しません。これは理想気体の分子間力がゼロであるという仮定から導かれます。したがって、理想気体では等温膨張や等温圧縮を行っても比エンタルピーは変化しません。
h = h(T)のみ
計算式も比較的シンプルで、定圧比熱を用いた積分で求められます。
一方、実在気体では分子間力の影響があり、圧力の変化によっても比エンタルピーが変化します。
h = h(T, P)
特に高圧や低温の条件では、理想気体からのずれが顕著になります。実在気体の比エンタルピーを正確に求めるには、状態方程式(例:van der Waals方程式、Redlich-Kwong方程式など)や、実験データに基づく相関式が必要です。
理想気体として扱った場合:
比エンタルピー変化Δh = 0(温度が一定のため)
実在気体として扱った場合:
比エンタルピーはわずかに増加します。ただし、空気の場合、常温・常圧付近では理想気体に近い挙動を示すため、この変化は非常に小さく、多くの実用計算では無視できます。
一方、水蒸気やCO₂、冷媒などでは、実在気体効果が大きくなり、圧力による比エンタルピー変化を無視できません。
理想気体として扱えるかどうかの判断基準として、換算圧力Prと換算温度Trがあります。
Pr = P / Pc(Pcは臨界圧力)
Tr = T / Tc(Tcは臨界温度)
一般に、Pr < 0.1 かつ Tr > 2 程度であれば、理想気体として扱っても十分な精度が得られます。
実務では、使用する物質と条件に応じて、理想気体近似で十分か、実在気体として扱うべきかを判断することが重要です。
比エンタルピーの実践的な使い方と応用例
続いては、比エンタルピーの実践的な使い方と応用例を確認していきます。
熱交換器の設計における活用
熱交換器は、高温流体から低温流体へ熱を移動させる機器であり、比エンタルピーを用いることで伝熱量や必要な流量を計算できます。
熱交換器の基本的なエネルギー収支式は以下の通りです。
高温側:Qh = ṁh(h1 – h2)
低温側:Qc = ṁc(h4 – h3)
ここで、Qは伝熱量、ṁは質量流量、添え字1、2は高温側の入口と出口、3、4は低温側の入口と出口を表します。
理想的な熱交換器では、熱損失がないため、Qh = Qcとなります。
ṁh(h1 – h2) = ṁc(h4 – h3)
条件:
– 水の流量:1000 kg/h
– 水の入口温度:20℃(比エンタルピー:約84 kJ/kg)
– 水の出口温度:60℃(比エンタルピー:約251 kJ/kg)
– 使用蒸気:150℃の飽和蒸気(比エンタルピー:約2746 kJ/kg)
– 蒸気凝縮後:150℃の飽和水(比エンタルピー:約632 kJ/kg)
必要な熱量:
Q = 1000 × (251 – 84) = 167,000 kJ/h = 46.4 kW
必要な蒸気流量:
ṁsteam = 167,000 / (2746 – 632) = 79.0 kg/h
このように、比エンタルピーを用いることで、必要な蒸気量を簡単に計算できます。
実際の設計では、熱交換器の効率や熱損失も考慮する必要がありますが、基本的な計算の考え方は同じです。比エンタルピーの差が大きいほど、少ない流量で多くの熱を移動させることができます。
冷凍サイクルやヒートポンプでの応用
冷凍サイクルとヒートポンプは、比エンタルピーを用いた解析が最も重要となる分野の一つです。これらのシステムは、冷媒が蒸発と凝縮を繰り返しながら熱を運ぶ仕組みです。
標準的な蒸気圧縮式冷凍サイクルは、以下の4つの過程から構成されます。
1. 圧縮過程(1→2):コンプレッサーで冷媒蒸気を圧縮
2. 凝縮過程(2→3):高温高圧の冷媒が熱を放出して液化
3. 膨張過程(3→4):膨張弁で圧力を下げる
4. 蒸発過程(4→1):低温低圧の冷媒が熱を吸収して蒸発
各過程での比エンタルピー変化から、性能を評価できます。
冷凍能力(蒸発器での吸熱量):
Qe = ṁ(h1 – h4)
圧縮機の仕事:
W = ṁ(h2 – h1)
凝縮器での放熱量:
Qc = ṁ(h2 – h3)
成績係数(COP: Coefficient of Performance)は、投入した仕事に対する冷凍能力の比です。
COP = Qe / W = (h1 – h4) / (h2 – h1)
ヒートポンプの場合も基本的な考え方は同じですが、目的が異なります。冷凍機は低温部から熱を取り出すことが目的ですが、ヒートポンプは高温部へ熱を供給することが目的です。
ヒートポンプのCOPは次のように定義されます。
COPhp = Qc / W = (h2 – h3) / (h2 – h1)
エネルギー収支計算での使い方
プラントや工場全体のエネルギー収支を評価する際にも、比エンタルピーは重要な役割を果たします。
複雑なシステムでは、複数の機器が接続されており、物質とエネルギーの流れを追跡する必要があります。このとき、各流路での比エンタルピーと質量流量の積を計算することで、エネルギーフローを定量化できます。
エネルギー収支の基本式:
Σ(ṁin・hin) + Q + W = Σ(ṁout・hout)
左辺は系に入るエネルギー、右辺は系から出るエネルギーを表します。
1. ボイラー入口(給水):150℃、10 MPa、h ≈ 632 kJ/kg、流量100 kg/s
2. ボイラー出口(高温蒸気):550℃、10 MPa、h ≈ 3500 kJ/kg、流量100 kg/s
3. タービン出口(低圧蒸気):50℃、0.01 MPa、h ≈ 2450 kJ/kg、流量100 kg/s
4. 復水器出口(給水):50℃、0.01 MPa、h ≈ 209 kJ/kg、流量100 kg/s
ボイラーでの加熱量:
Qboiler = 100 × (3500 – 632) = 286,800 kW
タービンでの仕事:
Wturbine = 100 × (3500 – 2450) = 105,000 kW
サイクル効率:
η = Wturbine / Qboiler = 105,000 / 286,800 = 36.6%
このように、各点での比エンタルピーを用いることで、システム全体の性能を詳細に分析できます。
エネルギー収支計算は、省エネルギー対策の検討や、プロセス改善の効果予測にも活用されます。どの機器でどれだけのエネルギーが消費または回収されているかを可視化することで、改善余地を見つけることができます。
また、環境負荷評価においても、燃料消費量やCO₂排出量の計算に比エンタルピーが用いられます。投入エネルギーと有効利用エネルギーの比率を分析することで、エネルギーの質的な評価も可能になります。
まとめ 比エンタルピーの単位や計算・求め方・使い方を解説!
比エンタルピーは、単位質量あたりのエンタルピーを表す重要な熱力学的状態量です。流体が流れる系でのエネルギー収支を考える際に不可欠な概念であり、温度と圧力によってその値が決まります。
SI単位系では主にkJ/kgが使用され、蒸気表やモリエル線図といったツールを用いて実際の値を求めることができます。理想気体では温度のみの関数となりますが、実在気体では圧力の影響も考慮する必要があります。
熱交換器、冷凍サイクル、ヒートポンプ、発電プラントなど、様々な熱機器やエネルギーシステムの設計・性能評価において、比エンタルピーは中心的な役割を果たしています。各機器の入口と出口での比エンタルピー差を計算することで、必要な熱量や仕事量、さらには効率まで求めることができます。
比エンタルピーの概念を正しく理解し、適切に活用することで、熱力学の問題解決や実務での設計計算がより確実かつ効率的に行えるようになります。本記事で解説した基礎知識と計算方法を、実践の場でぜひ活用してください。