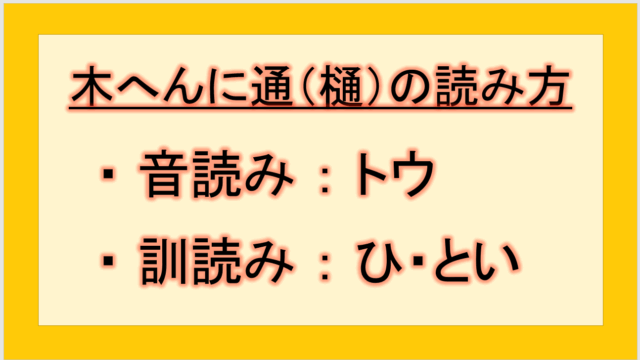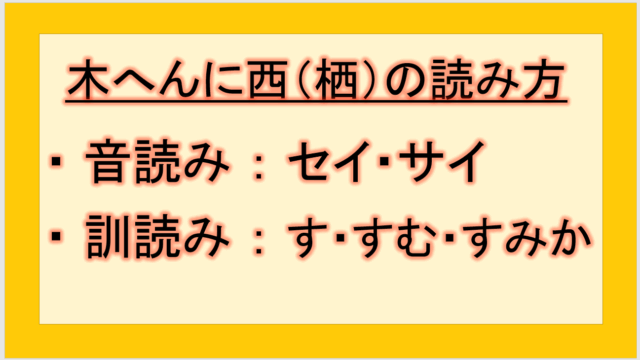この記事では、「告へんに鳥(鵠)」の漢字について、読み方、意味、由来、部首、画数、さらに「鵠」の読み方について詳しく解説していきます。
なお、面白い例文も多く紹介しておりますので、楽しみながら難しい漢字の読みなどを自然と覚えられると思います(^^)/
結論として、「告へんに鳥(鵠)」の読み方は以下の通りです。
・ 音読みは「コク」「ゴク」「ゴウ」
・ 訓読みは「くぐい」「しろ(い)」「まと」
※部首について、実際には「告へん」ではなく「鳥部(とりへん)」に分類されます。
それでは鵠の他の項目についても詳しく見ていきましょう!
告へんに鳥(鵠)の漢字の読み方は?
まず、「告へんに鳥(鵠)」の漢字の読み方を確認していきます。
上記の通り、
・ 音読みは「コク」「ゴク」「ゴウ」
・ 訓読みは「くぐい」「しろ(い)」「まと」
と読みます。
「鵠」の読み方は、基本的には「くぐい」と読みますが、熟語では「コク」という音読みでも使われます。また、「おおとり」と読むこともあります。
告へんに鳥(鵠)の漢字の意味や由来・成り立ちは?
続いては、告へんに鳥の「鵠」という漢字の意味や由来・成り立ちも見ていきましょう!
意味としては、訓読みからも理解できますが、
・ 白鳥の一種、コハクチョウやオオハクチョウなど
・ 的の中心、目標の中心
・ 物事の要点や核心
これらを表しています。
由来や成り立ち
「告へん」(実際には「こう(口+ム)」という形)は本来、喉や首の部分を表す部首要素で、「鳥」はそのままの意味です。
この二つの要素が組み合わさることで、「首や喉が特徴的な鳥」という意味が生まれました。これが白鳥などの首の長い水鳥を指すようになりました。
古代中国では、白鳥は神聖な鳥とされ、その姿から「鵠」という漢字が作られました。首の長さと白い美しさが特徴とされています。
また、「鵠」は弓術において的の中心を指す言葉としても使われるようになりました。これは白鳥の目を射るという弓術の究極の技から来ているとされています。
これらから転じて、現代でも使用される意味として
・ 白鳥などの水鳥の一種
・ 目標や的の中心
・ 物事の本質や核心を突いていること
になったといえますね(^^)/
以下の例文を元にマスターしていきましょう。
告へんに鳥(鵠)の漢字の読み方を理解しやすい例文紹介!
告へんに鳥(鵠)の意味や読み方を自然と覚えられる例文を以下で紹介します。
一般的な読みのものから、面白い例文までさまざま紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください(^^)/
告へんに鳥(鵠)の漢字を用いた例文
- 彼の発言は的鵠(てきこく)を射ている。
- 鵠的(こくてき)を得た回答だ。
- 命中鵠的(めいちゅうこくてき)の批評で相手を黙らせた。
- 青鵠(せいごく)という鳥は中国の古典に登場する。
- 白鵠(はくごう)が湖面に静かに浮かんでいる。
- 冬の湖に鵠(くぐい)が飛来する光景は美しい。
- 鵠沼(くげぬま)海岸は藤沢市の有名な観光地だ。
- 雪のように鵠(しろ)い翼が空を舞った。
- 鵠(しろ)き羽を広げて飛ぶ姿は神々しい。
- 弓道では鵠(まと)を正確に射ることが求められる。
告へんに鳥(鵠)の漢字を使った熟語は?
「鵠」を使った熟語には以下のようなものがあります。
的鵠(てきこく)
弓矢で射る的の中心。転じて、物事の核心や本質。
鵠的(こくてき)
的鵠と同じく、物事の要点や核心。また、目標とするもの。
命中鵠的(めいちゅうこくてき)
的の中心に命中すること。転じて、物事の核心を正確に捉えること。
白鵠(はくこく)
白鳥。特に白いハクチョウ類を指す。
これらの熟語も覚えておくと、「鵠」の意味をより深く理解できますね。
告へんに鳥(鵠)の漢字の部首と画数は?
告へんに鳥(鵠)の漢字の部首と画数も見ていきます。
結論として
・部首:鳥部(とりへん)
・画数:18画(総画)
ですね。
実際には「告へん」ではなく「鳥部(とりへん)」に分類されることに注意しましょう。
画数も多いので、丁寧に書きましょう(^^)/
まとめ 告へんに鳥(鵠)の漢字の読み方や部首や画数は?鵠では?
ここでは、告へんに鳥(鵠)の漢字の読み方は?意味・由来・部首・画数は?【鵠の読み方も:告へんに鳥】について、面白い例文も用いつつ解説しました。
日本語の漢字は奥深く、「鵠」の成り立ちを知ることで、さらに日本語の豊かな表現の幅を広げることができますね。特に「的鵠を射る」のような慣用表現は、日常会話や文章でも使われることがあるため、その意味や由来を理解しておくと役立ちます。
また、部首については「告へん」ではなく「鳥部(とりへん)」に分類されることも覚えておきましょう。「告」の部分は「こう(口+ム)」という形で構成要素となっています。
これからも様々な漢字に触れ、日本語の魅力を発見していきましょう♪