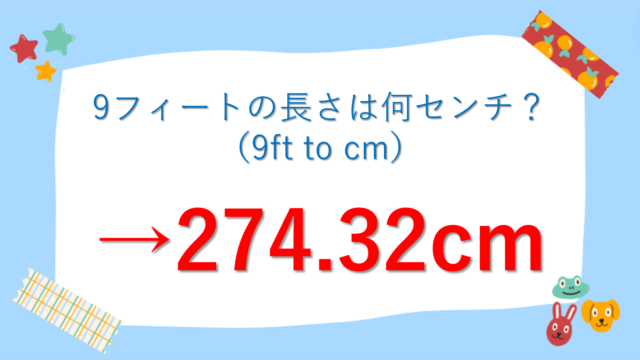電磁気学や電気工学を学ぶ上で重要な概念の一つが誘電率です。コンデンサ、絶縁体、高周波回路など、電気に関する現象を理解するためには、誘電率の知識が欠かせません。
しかし、誘電率とは何を表しているのか、どんな単位で表されるのか、比誘電率とどう違うのか、わかりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。
実は、誘電率は物質が電場をどれだけ通しやすいか、または電気を蓄える能力を表す物理量であり、材料の電気的性質を知る上で非常に重要な指標です。
水は誘電率が非常に大きく、空気や真空はほぼ同じ誘電率を持ちます。
この記事では、誘電率の基本的な定義から、単位や記号、真空の誘電率、計算方法や公式、比誘電率との違い、そして様々な物質の誘電率一覧まで、わかりやすく丁寧に解説していきます。
電気工学や物理学を学ぶ方はぜひ最後までお読みください。
誘電率とは?基本的な意味と定義
それではまず、誘電率の基本的な意味と定義について解説していきます。
誘電率の定義
誘電率(ゆうでんりつ、英語:permittivity)とは、物質が電場をどれだけ通しやすいか、または電気を蓄える能力を表す物理量です。
記号ではε(イプシロン)で表されます。
誘電率が大きい物質ほど、電場の影響を受けやすく、電荷を蓄えやすい性質を持ちます。
逆に誘電率が小さい物質は、電場の影響を受けにくいということになります。
例えば、水は誘電率が非常に大きいため、極性分子として電場に強く反応します。一方、空気やプラスチックは誘電率が比較的小さいです。
誘電率は、コンデンサの設計、絶縁材料の選定、高周波回路の設計など、様々な電気・電子機器の開発に欠かせない物理量です。
電束密度と電場の関係
誘電率を理解するには、電束密度と電場の関係を知る必要があります。
電場Eは、電荷によって作られる電気的な場です。単位はV/m(ボルト毎メートル)またはN/C(ニュートン毎クーロン)で表されます。
電束密度Dは、単位面積あたりを貫く電気力線の密度です。単位はC/m²(クーロン毎平方メートル)で表されます。
これらの関係は、次の式で表されます。
この式が示すのは、「電束密度Dは、誘電率εと電場Eの積に等しい」ということです。
つまり、誘電率εは、
という関係式で定義されます。
同じ電場Eを加えても、物質によって生じる電束密度Dが異なるのは、誘電率εが異なるためです。
誘電率が表す物質の性質
誘電率は、物質の電気的な性質を表す重要な指標です。
誘電率が大きい物質:
・電荷を蓄えやすい
・コンデンサの容量が大きくなる
・電場を弱める効果が大きい
・例:水、チタン酸バリウム、セラミック
誘電率が小さい物質:
・電荷を蓄えにくい
・良い絶縁材料になる
・電場の影響を受けにくい
・例:空気、テフロン、ポリエチレン
誘電率は、コンデンサの容量Cを決める重要な要素です。
平行板コンデンサの容量は、
ここで、Aは極板の面積、dは極板間の距離です。
誘電率εが大きいほど、同じ大きさのコンデンサでも大きな容量を得られます。
・誘電率が大きい:電荷を蓄えやすい(コンデンサに適する)
・誘電率が小さい:電荷を蓄えにくい(絶縁材料に適する)
・誘電率はコンデンサの容量を決定する
誘電率の単位と記号
続いては、誘電率を表す単位と記号について確認していきます。
誘電率の単位(F/m)
誘電率の単位は、SI単位系ではF/m(ファラド毎メートル)です。
これは、ε = D/Eという定義式から導かれます。
・電束密度Dの単位:C/m²(クーロン毎平方メートル)
・電場Eの単位:V/m(ボルト毎メートル)
したがって、
ここで、C/V = F(ファラド、静電容量の単位)なので、
ε = F/m
ファラド(F)は静電容量の単位で、電気工学では重要な単位です。
1ファラドは、1ボルトの電圧で1クーロンの電荷を蓄えることができる容量です。
真空の誘電率ε₀
真空(何もない空間)での誘電率は、真空の誘電率または電気定数と呼ばれ、記号ε₀(イプシロンゼロ、イプシロンノート)で表されます。
真空の誘電率の値は、
≈ 8.85 × 10⁻¹² F/m
です。この値は定数であり、どこでも同じ値を持ちます。
別の表現として、
ここで、k = 8.988 × 10⁹ N·m²/C²(クーロンの法則の比例定数)
真空の誘電率は、光速度cや真空の透磁率μ₀と次の関係があります。
この関係式は、電磁波(光)の速度が誘電率と透磁率によって決まることを示しています。
比誘電率とは
実際の計算では、比誘電率εᵣ(イプシロンアール)がよく使われます。
比誘電率は、真空の誘電率に対する物質の誘電率の比で、次のように定義されます。
または、
ε = εᵣε₀
比誘電率は無次元数(単位のない数)です。真空の比誘電率はεᵣ = 1です。
比誘電率を使うと、物質の電気的性質を直感的に理解しやすくなります。
・εᵣ = 1:真空と同じ
・εᵣ > 1:真空より電場を通しやすい(ほとんどの物質)
・εᵣ
これらの関係を理解することが、電磁気学の基礎となります。
誘電率の求め方と計算方法
続いては、誘電率を実際に求める方法を見ていきます。
基本的な計算式
誘電率εの基本的な求め方は、定義式を使います。
電束密度Dと電場Eを測定できれば、誘電率を計算できます。
ε = D/E = 7.08 × 10⁻⁸ C/m² / 1000 V/m
= 7.08 × 10⁻¹¹ F/m
この物質の誘電率は7.08 × 10⁻¹¹ F/mです。
また、コンデンサの容量Cから誘電率を求めることもできます。
平行板コンデンサの場合、
ここから、
ε = Cd/A
ここで、Aは極板の面積、dは極板間の距離です。
比誘電率の求め方
比誘電率εᵣは、誘電率εがわかれば簡単に求められます。
εᵣ = ε/ε₀
= 7.08 × 10⁻¹¹ / 8.854 × 10⁻¹²
≈ 8.0
比誘電率は約8です。
逆に、比誘電率から誘電率を求めることもできます。
ε = εᵣε₀
= 80 × 8.854 × 10⁻¹²
≈ 7.08 × 10⁻¹⁰ F/m
誘電率は約7.08 × 10⁻¹⁰ F/mです。
具体的な計算例
実際的な問題での計算例を見ていきましょう。
極板の面積A = 0.01 m²、極板間の距離d = 0.001 m(1 mm)の平行板コンデンサに、比誘電率εᵣ = 4のガラスを挿入したとき、容量Cは?
C = εA/d = εᵣε₀A/d
= 4 × (8.854 × 10⁻¹²) × 0.01 / 0.001
= 4 × 8.854 × 10⁻¹² × 10
= 3.54 × 10⁻¹⁰ F
= 354 pF
容量は約354ピコファラドです。
真空中で容量C₀ = 100 pFのコンデンサに、比誘電率εᵣ = 2.5の誘電体を満たしたとき、容量Cは?
C = εᵣC₀
= 2.5 × 100 pF
= 250 pF
容量は250ピコファラドになります。比誘電率の倍だけ容量が増加します。
比誘電率εᵣ = 6の物質中で電場E = 500 V/mのとき、電束密度Dは?
D = εE = εᵣε₀E
= 6 × (8.854 × 10⁻¹²) × 500
= 2.66 × 10⁻⁸ C/m²
電束密度は約2.66 × 10⁻⁸ C/m²です。
・ε = D/E(定義式)
・εᵣ = ε/ε₀(比誘電率)
・ε = εᵣε₀(誘電率の計算)
・ε₀ = 8.854 × 10⁻¹² F/m(覚えておく)
・C = εA/d(平行板コンデンサ)
これらの式を使いこなせれば、様々な電気の問題を解けます。
様々な物質の誘電率一覧
続いては、代表的な物質の誘電率を確認していきます。
気体の誘電率
気体の誘電率は、真空とほぼ同じで非常に小さいです。
真空:
・比誘電率εᵣ = 1(定義)
・誘電率ε₀ = 8.854 × 10⁻¹² F/m
空気:
・比誘電率εᵣ ≈ 1.00059
・実用上はεᵣ = 1とする
・誘電率ε ≈ ε₀
窒素:
・比誘電率εᵣ ≈ 1.00055
酸素:
・比誘電率εᵣ ≈ 1.00049
二酸化炭素:
・比誘電率εᵣ ≈ 1.00092
気体の比誘電率は1に非常に近く、実用上は真空と同じとして扱われます。
液体の誘電率
液体の誘電率は、物質によって大きく異なります。
水:
・比誘電率εᵣ ≈ 80(室温)
・最も高い誘電率を持つ一般的な液体
・優れた溶媒として機能
エタノール:
・比誘電率εᵣ ≈ 24
アセトン:
・比誘電率εᵣ ≈ 21
メタノール:
・比誘電率εᵣ ≈ 33
グリセリン:
・比誘電率εᵣ ≈ 43
変圧器油:
・比誘電率εᵣ ≈ 2.2〜2.5
・絶縁油として使用
ベンゼン:
・比誘電率εᵣ ≈ 2.3
水の誘電率が特に大きいことは重要です。これは水分子が極性を持つためです。
固体の誘電率
固体の誘電率は、材料によって幅広い範囲にわたります。
絶縁材料:
・テフロン(PTFE):εᵣ ≈ 2.1
・ポリエチレン:εᵣ ≈ 2.3
・ポリプロピレン:εᵣ ≈ 2.2
・ポリスチレン:εᵣ ≈ 2.6
・塩化ビニル:εᵣ ≈ 3〜4
ガラス・セラミック:
・石英ガラス:εᵣ ≈ 3.8
・パイレックスガラス:εᵣ ≈ 4.7
・普通ガラス:εᵣ ≈ 5〜10
・磁器:εᵣ ≈ 6〜7
・マイカ:εᵣ ≈ 5〜7
高誘電率材料:
・チタン酸バリウム:εᵣ ≈ 1000〜10000
・チタン酸ストロンチウム:εᵣ ≈ 300
・酸化チタン:εᵣ ≈ 85〜170
その他の材料:
・紙:εᵣ ≈ 2〜4
・木材(乾燥):εᵣ ≈ 2〜7
・ゴム:εᵣ ≈ 2〜4
・氷:εᵣ ≈ 3.2
・ダイヤモンド:εᵣ ≈ 5.7
・シリコン:εᵣ ≈ 11.7
| 物質 | 比誘電率εᵣ | 用途 |
|---|---|---|
| 真空 | 1 | 基準 |
| 空気 | ≈ 1 | 一般環境 |
| テフロン | 2.1 | 高周波絶縁 |
| ポリエチレン | 2.3 | ケーブル絶縁 |
| ガラス | 4〜10 | 一般絶縁 |
| エタノール | 24 | 溶媒 |
| 水 | 80 | 溶媒 |
| チタン酸バリウム | 1000〜10000 | 高容量コンデンサ |
空気と真空の誘電率がほぼ等しいため、空気中での計算は真空として扱えることが多いです。
まとめ 誘電率の水や真空の一覧・比誘電率との違い!求め方や公式
誘電率について、基本的な定義から単位、計算方法、様々な物質の誘電率まで詳しく解説してきました。
誘電率εは、物質が電場をどれだけ通しやすいか、または電気を蓄える能力を表す物理量で、D = εEという関係式で定義されます。
単位はF/m(ファラド毎メートル)です。
真空の誘電率ε₀ = 8.854 × 10⁻¹² F/mは基準となる重要な定数です。
実際の計算では、比誘電率εᵣ = ε/ε₀がよく使われ、これは無次元数で物質の電気的性質を表します。
誘電率の求め方は、ε = D/Eという定義式から計算するか、ε = εᵣε₀という関係式を使います。
比誘電率がわかれば、誘電率を簡単に求められます。
物質の誘電率は、水(εᵣ ≈ 80)やチタン酸バリウム(εᵣ ≈ 1000〜10000)が非常に大きく、空気、テフロン、ポリエチレンなどは小さい値です。
誘電率が大きい物質はコンデンサに、小さい物質は絶縁材料に適しています。
コンデンサ、ケーブル、絶縁材料など、多くの電気機器の設計には誘電率の知識が不可欠です。
この記事で学んだ知識を使って、電気工学の理解を深めてください。